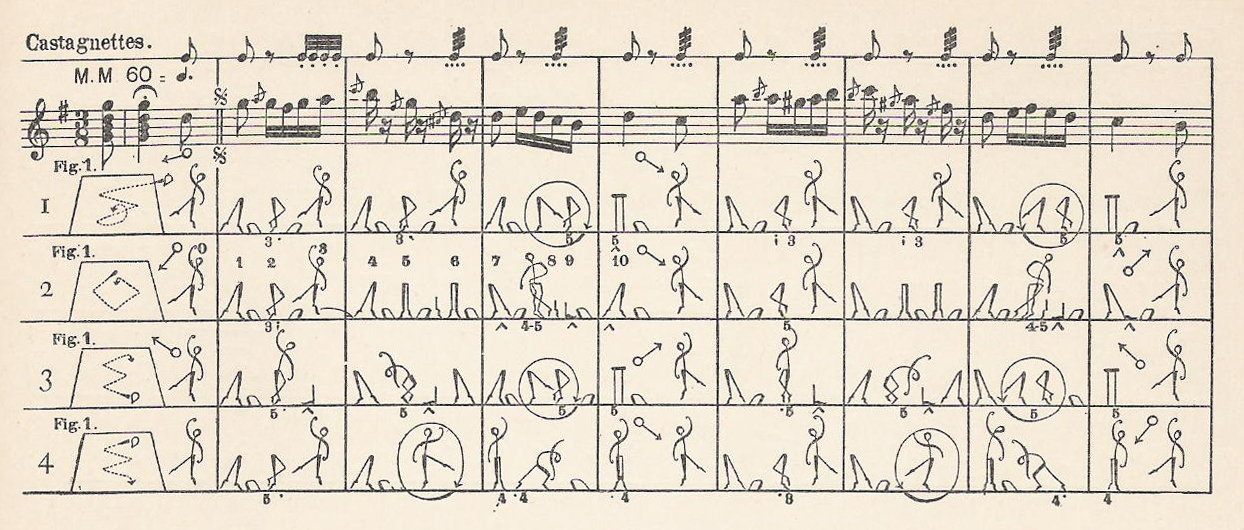2016/08/12
岸井大輔さんは、現在、日本の芸術の現場で特異な形で活躍しているアーティスト。カオス*ラウンジや篠田千明のクリエイションのいわば「助言者」として知られているように、岸井さんの周りにはいま多くの若い作家たちが集い、芸術をめぐる質の高い実践と考察を重ねています。その背景にあるのは、岸井さんがずっと続けてきた、地域をリサーチして、その成果を演劇をベースとしつつさまざまなメディアで上演する、という活動です。2000年代初頭から開始された「散歩をしながら楽しむライブ」と称される演劇「POTALIVE」は、その代表例。舞台/客席の固定された関係に縛られる劇場から離れ、演劇が街に出ることは、自ずと、その街から多くの刺激をえることになるでしょう。インタビューの中で岸井さんはそれを「変化」という言葉でまとめていますが、創作者に「変化」を与える「リサーチ」の力について、岸井さんは多くの実践を通して実感してきたはずです。
今回、BONUSは「地域」を「リサーチ」するダンスの可能性について、岸井さんといくつかの視点から考察し、またそこから得たアイディアを多くの作家がシェア可能な「使えるもの」にしていきたいという目論見のもと、岸井さんへのインタビューを行いました。対話は、私が想定した枠をダイナミックに越えていく場面も多々ありますが、その点も併せてお読みください。(収録: 2016.4.11@渋谷)
岸井さんの演劇と「リサーチ」の関係

岸井さんは演劇の分野での活動を「リサーチ」をベースに行ってきました。劇場での公演にこだわらずに、「リサーチ」の現場での上演や地域に根ざした会場での上演という意味でも、ユニークな活動歴を重ねてきた作家ですよね。私は、そんな岸井さんと一緒に〈「リサーチ」をベースに創作するダンスというものの可能性〉について考えてみたいと思い、このような対話の時間を作っていただきました。今日はありがとうございます。さて、岸井さん、ぼくは美術や演劇に比べて「リサーチ」を重視する意識がダンスには弱く、それが一種の「遅れ」のように感じてもいるのですが、岸井さんの目にはダンスの状況はどのように映っているのでしょうか。

なるほど。おっしゃることはわかる気もしますが、僕が「POTALIVE」★1をはじめたとき、リサーチをして創ることにつきあい、実践をしてくれたのはダンサーたちだったんですよ。「POTALIVE」は、そもそもケイタケイさんのところにいた舞踊家の木室陽一さんと一緒にやっていたわけですし。当初はダンスの人しかリサーチに付き合ってくれなかったんです。
- ★1
- 「POTALIVE」: 「散歩をしながら楽しむライブ」のこと。サイト には「軽いサイクリングや散歩を表すポタに、演奏・演技、ダンスなどを表すライブを組み合わせて作った造語です。」とある。

えっ。あー。面白いお話ですね。

そうなんです。2000年ごろは、僕の周囲の演劇人や美術家に「リサーチ」をベースにする作品を作りたいといってもピンと来てくれる人少なくて。興味を持ってくれた人はダンサーばかりでした。

予想に反したお話です。なるほど。

「POTALIVE」に限らず、僕は創作するとき、手探りで未知の世界を進んでいきます。創作は一般にそういうものだと思うのですが。たとえば「POTALIVE」のころは、〈「人間の集団」を素材とする表現は全部演劇じゃないか?〉と考え、人間の集団の例として、地域そのものを観たり歩いたりする演劇もできるんじゃないかという仮設を元に創っていた。で、地域のリサーチをしていたんです。どんな作品になるかわからないのにただリサーチと称して散歩ばかりしているんですから、いっしょにやる人は不安でしょう。「POTALIVE」当時、この探索を面白がって付き合ってくれたのは、木室くん以下ダンサーのみなさんでした。でも、最近は美術家が多いです。たとえば「日本列島にすんでいる人の振舞」のリサーチと創作をしている「始末をかく」メンバーは去年まで美術家ばかりでした。きっと、あるジャンルの改革期にそのジャンルにいる人は、自分にとってわからないことに向き合うのが好きな人が多くなるんじゃないかな。演劇だから、ダンスだから、ではなくて。
しかも、「POTALIVE」を創っているとき、ぼくが考え込んで進まなくなると、一緒に作業をしているダンサーさんたちのおかげでジャンプできることがよくありました。

それはなんでなんでしょう。

例えば、ぼくには最初、宗教が関わる作品を創ることに躊躇があったんですよ。「ロマンチック」でダサいんじゃないかとか、「伝統主義的」になるんじゃないか、とか。でも、ダンサーと一緒にお寺とかに行くとすぐに踊ってくれるんですよ。

ダンサーはあまり場所に頓着しないんですかね(笑)。

いや、逆に、ダンサーのほうが、僕よりも、場所そのものとちゃんと向き合っていたと思います。僕とは違うリサーチをするんです。たとえば宗教施設には儀礼的動作とか、方向の意味とか、身体的な情報が多いでしょう。それを実際にやってみて、身体を通して調査していくんです。で、僕が不安に感じていたようなことを見事に避けた精確な表現があらわれる。

ダンサーの身体を媒介にしたリサーチというのは、興味深いですね。

はい。そのリサーチで生み出されたダンスのおかげで、僕こそがあまり場所に頓着しない妄想を作品にできました。ダンサーはぼくが想定していたのとは別のルートでの現実へのアプローチを教えてくれた。もちろん、僕も彼らと違う方法で現実をリサーチできる。美術とか、音楽とか、それぞれのジャンルは、現実と付き合いリサーチする異なる方法をもっているからこそ違うジャンルなんじゃないかと思っています。

いまのお話のように、今回僕が岸井さんとの対話で見つけたいと思っているのは、リサーチを具現化する際のダンスというメディアの力の有り様なんです。とくに、岸井さんは演劇のひとで僕はダンスに関わってきた人間ですが、演劇というメディアと比較したり、照らし合わせることで、その有り様がくっきりと見えてこないかと望んでいます。

僕の考えでは、演劇とダンスは素材が違う。演劇は人間集団であり、ダンスは身体なんです。無論、身体は集団に影響されるでしょうけど。例えば、鈴木ユキオさんは内蔵の位置にこだわって作品を作っていたりするじゃないですか。あれはすごくダンス的だなと思うんですね。身体というメディウムにスペシフック。対して演劇は集団を扱います。人間って、個人では割と、合理的で自由なんだけれど、集団になると途端に愚かで不自由になりますよね。戦争とか。個人的に戦争したい人ってそんなにいないと思うんですよね。人間集団は、人間個人とか身体とは異なる性質をもっているとみなせる。で、演劇は人間集団を素材としてきたと思います。

ダンスの素材は身体で、演劇の場合は集団だと。

ダンスは身体を扱うからか、多くのダンサーは身体の感覚に精確に表現するのが大事ということを体現してくれている。結果主体的で自由な個人の表現になることが多いんだと思います。なので、僕は作家性とは何かでさえ、美術からではなく、ダンスから教わったと思う。

なるほど。確かに、ダンサーって「いつも自分の身体と対話して創作するひとたち」ですよね。自分の身体へとフィードバックを重ねながら、自分はどうするべきかを思案しているひとたちですよね。その分、他人に煩わされない自由さがあるのかもしれない。そのことには、良さもあるとは思うけれど、またそのことがネガティヴに映る時もあります。自分との対話へと閉じこもっている自閉的な部分もある。だから「もっと開いたら?」と思うこともある。リサーチを基にしたダンス創作というものは、社会に対して自分を開いていく作業ですから。ただし、その閉じる力が必要な場合もありますよね。

最近、美術のひとたちとの仕事が多いのは、いま日本の美術は悩まなきゃいけない時期ということかもしれない。で「悩む」ときって、自分のことだけ考えていても行き詰るから、他者のことを知る、つまり「リサーチ」しなきゃいけなくなりますよね。

そうですね。いまの自分にないものを求めて「悩む」わけですものね。自分の中に蓄えを作る手段にリサーチがあるとして、「リサーチ」という方法に僕が注目しているのは、自家中毒的になってしまいがちな作家に、その状態からブレイクスルーする手段として「リサーチ」があるということを考えてみて欲しいなあと思うからです。

クリエイションとは、自分も予想外のものを作るということでしょう。予想出来る範囲で作ることは、特段、創造という必要がない。だから、「関心があるから調べる」ではなくて「調べたら何かに関心をもつ」の順番が大事。自分の関心よりも広くものを見る。ジョン・ケージとかがやっていた「イベント」も同じようなことを志向していたと思うんです。

なるほど。

そういえば、この考えもまた、最初はコンテンポラリー・ダンスで知ったんですよ(笑)「コンタクト(インプロヴィゼーション)」を21歳のとき初めて見て。踊っている本人の想像を超えてダンスが創造されていく。こんな簡単な方法で予想外のところに行けるのかと思って。

「コンタクト(インプロヴィゼーション)」の方法に驚いたんですね。

コンタクトすることが調査手段じゃないですか。あと舞踏のひとたちがやる、自分を騙すテクニックとかね。手塚夏子さんにもそういうところがあると思う。「観察に基づく創造」を僕はダンスから教わったと思っているんだよなあ。

それは面白いですね。「コンタクト(インプロヴィゼーション)」ひとつ取っても、それが「コンタクト(接触)」と言っている時点で、他者に関わって、自分一人では得られないものを他者からもらってくる、あるいは他者との時間を創造していくことなのだとすると、すでにそこにはぼくが「リサーチ」という言葉を通して抱いているイメージが部分的に含まれているということになりますね。そう考えるとコンテンポラリーダンスの方法の中に、すでに「リサーチ」の要素は含まれていると。

そう思いますね。
戯曲と上演、そして上演形態としてのダンス

最近、ぼくがダンサーにアウトプットをお願いした活動に「TAble」があります。豊島区と東京都といっしょにやったプロジェクトで、5人のダンサーさんにアウトプットをお願いする予定だったんですが、プロジェクト全体が僕とは関係のない事情で消滅してしまい、3年計画のうちの1年分しか実現しなかった。1年目はリサーチ、2年目はアウトプット、3年目は振り返りと戯曲集制作の計画で進めていたので残念でした。リサーチしたのは豊島区の区界(くざかい)。豊島の文化事業はほとんど区の中心部、つまり池袋で行われているんだけれど、豊島区って実は、巣鴨とか雑司が谷とか長崎とか、全然違う特徴をもった地域の合併なんです。現在豊島区の中心とされている池袋はむしろかつてはどの地域から見ても辺境だった。それで空白地帯だったからこそ、いまのような都市ができたんですよ。だから、豊島区をリサーチするのならば、今では端っこになっている区界の文化を調べて作品にしていくのが楽しそうだと思ったんです。で、初年度のプロジェクト「diVISION」★2では15人のリサーチャーのチームを作り、それぞれのリサーチャーが掲げたテーマに沿って取材し、Googlemap上にピンを指して取材したものを公開していったんですね。ピンは区界上にたっていくので、結局線をなして豊島区をかたどるという仕掛けです。このリサーチ自体とても楽しかった。24時間かけて区界を一周するというイベントもやりました。
- ★2
- 「dVISION」: としまアートステーション構想の一環で2012年に行われたリサーチプロジェクト。

区の縁を歩いてパフォーマンスすると24時間かかるということに、まず驚きます。15人のリサーチャーのチームが活動したというお話もすごいですが、ただ豊島区に限らず、おそらくどんな地域でもリサーチを行うとその土地にまつわる多数の情報を集めることができるのでしょうね。さて、それをどのようにアウトプットすればよいと考えたのですか。

区界って道路の真ん中に丸く出っ張ってたりとか、アミダ状に家の間を縫っているとか、不思議な線で構成されているのです。が、調べてみると、変な形の線ひとつひとつに物語があるわけです。個人的な都合や、原始時代にさかのぼるような歴史や、政治的な問題が、ランダムに一本の線上に並んでいる状態が見えてきたんです。物語が線に並んで意味を生産している。これをアウトプットするならばダンスなんじゃないかと思ったわけです。

物語が線状になっているのが立ち現れてきた。その線を扱うのはダンサー、振付家ではないかと思ったというわけですね。

プロジェクトは中断されたんですが、リサーチのアウトプットはしたかったので、別の予算を確保して、2人のダンスアーティストに上演をお願いしました。磯島未来さんと小川水素さん。2人それぞれに去年のリサーチを、一緒に区界を歩いて伝えながら、作品を作ってもらう。

上演場所も区界で?

区界のそばの場所で。磯島さんは、みらい館大明っていう板橋区と豊島区の境を接するあたりにある閉校利用施設でその施設に集う人たちに振付けてもらい、小川さんは雑司ヶ谷駅の出口通路周辺で発表してもらった。

二人の作家のアウトプットにはどんな違いがあったんですか。

磯島さんはぼくらのリサーチからコミュニティの物語を生み出し、小川さんは振舞を線にするというやり方で取り組んでくれました。実現しなかったあとの3人もそうなんですが、違うタイプのダンス作家に創ってもらいたかったということがありました。

やはりアウトプットを一人ではなく複数の人に取り組んでもらうということには、岸井さんの思いがあったわけですよね。

ぼくが演劇ってものはそういうものだと思っているってことですね。

ああ、なるほど。身体を素材とするダンスが作家の集団として現れたときには、演劇という問題がそこに生じてくるということですね。「ダンス」や「演劇」は岸井さんにとって単なるジャンルではないということなのですね。

人はいろいろだっていうことを示すことが、まず重要だと思っているからですね。それぞれの振付家が別々に創っても、お客さんは複数のアウトプットを見ることになるでしょ。

ああ(笑)

ダンスは予定していた5人全部できなかったけど、少なくても1人じゃなくて、2人はやりたかった。でも、それとは別に、区界をテーマに、区界で見つけたテーマ別にトークイベントやワークショップを20回企画しました。それはそれでとても面白かったんですが、やはり磯島さんと小川さんの上演の方が、作業が先に進んでいく。上演作品にした方がよいのだなと思いました。

そう、その点をお聞きしたかったんです。ぼくは研究者ですが、研究者はある事象についてアカデミックなスキルを用いて調べ、テキスト原稿という形でアウトプットしますし、ジャーナリストはジャーナリストの、美術作家は美術作家のスキルを用いて調べ、各自の形式でアウトプットするわけですが、そうした諸々のやり方と比べて、ダンスというアウトプットには独自のどんな力があるのかという点を理解したいという気持ちが強くあります。

最今の日本のアートプロジェクトではドキュメンテーションをどうするかが流行っていて、僕もいくつかかかわったのですが、結局、写真を撮り、録音を再生もしくは文字にし、日付を正確に記す以上のことができない。正確かどうかという話にしかならないようなのです。でもこのやり方だと一番大事な、各自の個人的な体験はぬけてしまいます。たとえば、アートプロジェクトにが理由で転居したり結婚したり就職したりしているひとがいるんですが。

ああ(笑)アートプロジェクトをきちんと捉えるとしたら、そこで生じた体験の総体をちゃんと個別的に見ていく必要がありそうですね。しかも、そこには単なる鑑賞体験という次元では片付けられない出来事が、そうか、例えば「引っ越し」とか「結婚」とかが起きているわけですね。

多くのアートプロジェクトは引越しを引き起こすわけです。ある土地が気に入って引っ越してきてそこに暮らすという過程や感情の流れまで含めなければ、アートプロジェクトを記述したり批評したりすることができないわけです。だって、アートプロジェクトの重要な鑑賞者である地元住民は、これらの体験も含めてアートプロジェクトとして鑑賞しているし、作家は作品の一部として計画しているからです。引っ越してくる人たちの動機に批評性があるのか、とかまで織り込んで作品をつくっているアーティストは結構いますよ。だから、アートプロジェクトを批評するには、ご近所づきあいも含めて考察対象にしたほうがいい。だからといって、ご近所のインタビューをいくら並べてみても、劣化事実にしかならないわけです。

記録には体験の密度を再現できないという限界があるわけですね。

それに対して、まず、ダンスや演劇という上演芸術は、「記録じゃない」んですよね。上演はオン・ゴーイングなもので、体験だから。踊っている間はドキュメントじゃない、体験中です。ダンス鑑賞者の人生も上演の一部になるじゃないですか。記録じゃなくてライブで、今その状態であるということが、踊ることや舞台を作ることで如実に示されるわけです。上演は、今も続いていることとして捕らえなおす行為と言えると思います。

上演というものは、普通考えるに、ある状態を日常というものからいったん切り離して、劇場という空間に持ち込んで、日常と異なる特別なものとして観客の前に差し出すものである、ということでもあるじゃないですか。でも、いまの岸井さんの考えは、そうではなくて、上演というものがいったん自分と切り離した日常ともう一度地続きにするといるということですよね。

はい。生き返らせるという意味でのリプレゼンテーションです。
次に、「戯曲」ということを考えたいんですが、今話題になった切り離しのことだけれども、戯曲というのは切断だと思うんです。ぼくはこのことを考えるときには、リチャード・シェクナーが『パフォーマンス研究』★3で述べている「否定」と「二重否定」という概念が一番鋭いと思うので、この概念を使って話しますね。生きているものが記録化されるということは生きているものが死ぬわけです。その人の体験じゃないモノにする。でも、上演は、その人の体験じゃなくなったこと=否定をもう一回否定することになるわけです。切断したものをもう一回ライブにするっていうこと。だから単に地続きなんじゃなくて間に「否定」を介在しているわけです。
- ★3
- リチャード・シェクナー『パフォーマンス研究 演劇と文化人類学の出会うところ』(高橋雄一郎訳、人文書院、1998年)。「二重否定」についてシェクナーはこう述べている。「私の考えでウィニコット[イギリスの精神分析学者]の説を大胆に公式化してしまうと、赤ん坊や遊んでいる子供、それに芸術に触れている大人は、あるいくつかの物事や状態を「私ではないが、私でなくもないもの」として認識していることになる。オリヴィエはハムレットではないが、ハムレットでないものでもない。そしてその逆もまた正しい。『ハムレット』という戯曲の上演では、ハムレットはオリヴィエではないが、オリヴィエでないものでもない。この二重否定の領域では選択と仮想現実が常に活性化されている。」「儀礼、演劇、復元村、アグニチャヤナなど、再現された行動はすべて「過渡的な行動」である。「私でない」要素が「私でない」という性格を失うことなく、「私」になる。これは象徴的行為の特徴として欠かすことのできない二重否定性である。パフォーマーは自己を直接にではなく、パフォーマンスという媒体を通して、他者を体験することによって体験する。演技している間、パフォーマーは「私」ではなく、「私でなくはない」存在になる。この二重否定の関係は再現された行動が、同時に個人的であり社会的であることを示している。」(「行動の再現」『パフォーマンス研究』所収、p. 64)

ちょっとまとめてみます。ドキュメントというものは、客観性というか透明性を追求するという特徴があるわけですよね。誰でもわかるように記録して残す。でも、そうすると、体験そのものに近づくというよりは、体験そのものを逃してしまうことになりがちである。つまり、ドキュメントを読むことがある体験に近づくことのようでいて、その近づく行為が体験的ではなくなってしまうという自体を引き起こしてしまう。それに対して、上演はある体験を再開するためのものであり、というよりは体験そのものの再開であるわけですね。そう考えると、透明性を否定する(否定を否定する)わけだから、上演は自ずとドキュメンテーションのような分かりやすさを欠いており、不透明性が高まった表現となる。この、上演の、不透明であること自体が観客の出来事を体験の水準に導いている気がします。さて、とはいえ両者はまったく矛盾するものではなく、体験の再開を可能にする上演のためには、上演を進めるための何か、つまり戯曲が必要なのだというわけですね。

はい。なので、ぼくのいう戯曲は「台詞が書いてあるもの」ではなくて上演のもとになるもの全てです。だから、戯曲は生が無い文字のような物体だけど、上演は死んだ文字によってできた戯曲の死を否定しライブという生命を生み出し、二重否定すなわち肯定をする。それが戯曲の原型的な意味なんだと思う。この話でよく例に出すのは、対話編や論語のような偉人の記録を残しているものって戯曲形式ですよね。宗教的な体験って正確にドキュメントしても意味ないじゃないですか。将来的にもブッダの精神を残しておきたいんじゃないかと。

ソクラテスに会ったということを(後世のひとに)もう一回体験させたい。

そう。体験させたい。そのためにまとまっているのが戯曲なんだと思う。

ああ!

最初の問いに戻ると、ドキュメンテーションは単なる記録でもいいけど、戯曲はドキュメンテーションじゃなくて、「さあ、これから始めてください」といっているようなものです。

美術の分野でいう「インストラクション」あるいはダンスの「タスク」という概念に近い考えなんですかね。「行為を生成するために置かれたルール」というか。

だからぼくはこういう発想法もダンスとの付き合いから思いついているんですよね。

そうなんですね(笑)岸井さんのいう戯曲は、そうなると、ある意味でダンスの分野では振り付けといってもよいのかもしれませんね。

まあ、身体でのライブを狙う振り付けと違って、戯曲は集団を生き返らせることなので、根本的に違うと思いますけどね。他者との交流とか道徳も含めて蘇らせる。美術は、基本的に生きた体験を殺して永遠にしたいんだと思うんですよ。それはそれで素晴らしいと思うんだけれど、でも、ぼくはライブではない絵画を見たときに戯曲として見ちゃうんですよね。絵を生き返らせてライブにしてしまう。コトを否定したモノで、モノがコトを生み出せば戯曲といっていいと思うし、その知恵の集積が演劇史なんじゃないかな。
人間の集団としての演劇は政治的なかたちを反映する

集団の個々の違いがいきていて、かつ、集団全体を貫くものがある演劇がよいと思っているんですが、それはうまくいっている民主主義をよいと思っているということなんだなと最近気づいたんです。全員作家でありかつ全体で何かを作りたいひとの集合を見せるって、理想的な民主主義の提示ですよ。

BONUSが連結クリエイションという企画で作家にテーマを委ねる際に、必ず複数の作家にお願いしてきたんですね。一人の作家にお願いして、じっくりと時間も予算もかけて、大きな公演へと至るという道もあるとは思うのだけれど、ぼくが目指したのはそれではなかったんです。一つの課題に複数の答えが並置されている状態、それを生み出すことこそが、次の誰かのクリエイティヴィティの刺激剤になるのではないか。BONUSは何を作りたいかといえば、土壌を作りたいわけですが、それはそうした複数のアイディアの林立によって可能になると考えてきたわけです。ただそれを「民主主義」という言葉では考えてこなかったですね。

ぼくは演劇の形式を意識していく中で民主主義を志向していることに気づいたのです。演劇より大きな政治を考える中で民主主義的な作品を作ろうとしたのではなくて、演劇の趣味から民主主義を考えることに向かっていたんです。政治って、政治的であろうとしてそうなるもんじゃなくて、自分が知らないうちに、ある政治判断をしていたことに気がつくことからはじめるしかないんじゃないか。
たとえば岡田さんや前田さんが登場してきたときの二人が表現した身体や集団は結果として非正規雇用の実態を訴えていたと思います。リアリティを考えていった結果そうなのが重要だと思うのです。ですが『キレなかった14才♥りたーんず』★4の作家たちは 「非正規雇用が問題ならバイトなんかやめればいいじゃん」って感じさせた。そういう政治だと思った。
- ★4
- 『キレなかった14才♥りたーんず』: かつて「キレる14才」と言われた世代が集まった2009年の合同公演。

確かに、彼らの登場の瞬間、これまでとははっきり違うという感触がありましたよね。

狙って、じゃなくて、結果、ですよね。渋家と出会ったときに、リターンズの舞台で見たものの、現実の中でおきていると思った。渋家ではニートがゴロゴロしているんだけれど、ニートがいないとひっきりなしに来訪してくるお客さんに対応できないので、ニートはありがたがられているんです。

渋家を実体化しているのがニートなんだ。

そう。僕は人間の集団を素材とする表現は全部演劇と考えるので、渋家は演劇です。本人たちも作品っていっているし、演劇作品とみなしていいでしょう。だから岡田利規『フリータイム』(2008年)に対する応答が「ニートでOK!」の渋家だ、という演劇史が日本にはあると思っています。渋家の作家斉藤桂太の戯曲を篠田さんが演出すると聞いたとき、現代日本演劇史における重要な仕事だと思いました。でも、チームに入れてもらって創っているときは、そんなこと忘れてしまいます。で、「非劇」という形できてみると、とても政治的な作品になったな、と思っています。

ところで、ダンスは身体だという話に引きつけてみると、「リサーチャーとしてのダンサー」というものは、リサーチの最中で、身体を媒介にして社会に向き合うことになるわけですよね。その身体を抱えたリサーチャー=ダンサーというものは、どうやっても透明なニュートラルな存在になれるわけはなくて、どうしても不透明さを、個々の社会的な背景であるとかそれ固有の厚みを持たざるを得ないし、そのことによってリサーチの成果というものは自ずとバイアスがかかってくるということがあるわけです。その不透明さを無視することはできないですね。

人間が透明になれるなら、政治なんていりませんものね。リサーチをすると、自分の不透明な、政治的な立場が見えてくる。政治って他者とのかかわりだから、一人で考えていても見えてこないものなのです。

個々のリサーチャーの透明化されない実存的な厚みがリサーチというものに不可避的に付随してくるからこそ、一つの同じリサーチをベースにした複数の作家による上演というものが、重要になってくるのだと思うんですよ。
ただし、こんなことも思います。しばしば上演芸術を鑑賞していると、舞台上の演じ手が、こちらとのコミュニケーションを意識していないと感じさせられてしまう場面にでくわします。観客との関係が過剰に切断されているというか。単に接続されていれば良いということでもないのですが、目の前の観客がいるということ、そこに嫌が応にも接続してしまうにもかかわらず、そのことに意識が向けられていないこと、そういう側面の「不透明性」も気になります。

観客に対して「透明」になることに対する恐れがあるのかもしれません。他者は「不透明」なわからないものだから怖いですよね。でも、創造とは何かといえば「不透明な」「予想不能」なものを創ることだから、社会や観客という他者の群はリサーチに適している。

「リサーチ」というスタンスで社会や他者と向き合うのが難しいんですかね。

自分の想像と超えるものと向き合うのは難しいですよね。あるいは、単にクリエイトが怖いのかもしれませんね。でも、もしクリエイションをしたいなら、社会とか他者は自分の想像を超えていから、都合がいいと思いますよ。

なるほどこういうことなのでしょうか。「リサーチ」と「クリエイション」というものは、両者に大きな隔たりのあるもののようだし、そういう点は否定できないとしても、「クリエイション」には「リサーチ」が必要であるのならば、単純に別々のものとして考えることができないはずですね。例えば、「リサーチ」しました、では次に「クリエイション」しましょう、みたいに分けられるものではない、そこに誤解があってはならない。

「リサーチ」というのは食事であって、クリエイションの栄養です。材料。ご飯食べずに作ったって痩せていくだけでしょう。

リサーチすると力がみなぎるってことですかね。

ぼくが一番恐れるのは自家中毒です。つまり、偏食になることを恐れています。自分が好きじゃないものや興味がないものに対して、それと嫌々じゃない形で、びっくりしたとか好奇心が湧いたとか、そういう仕方で自分の興味のフレームの外にあるものを摂取することが大事だと思っています。

先にも、岸井さんは自分からリサーチ対象を選んだことがないとありましたね。そのことと関連していそうですね。

だってクリエイションが目的ならば、自分から選んでない対象をリサーチするほうが目的にかなっているわけでしょう。自分でも知らないものを作り、予想外のところに行くわけだから。だからぼくは他人を創作の動機にしているということですね。しかし、そういう態度こそ、尊敬するダンスアーティストたちから学んだものだと感じますけどね。