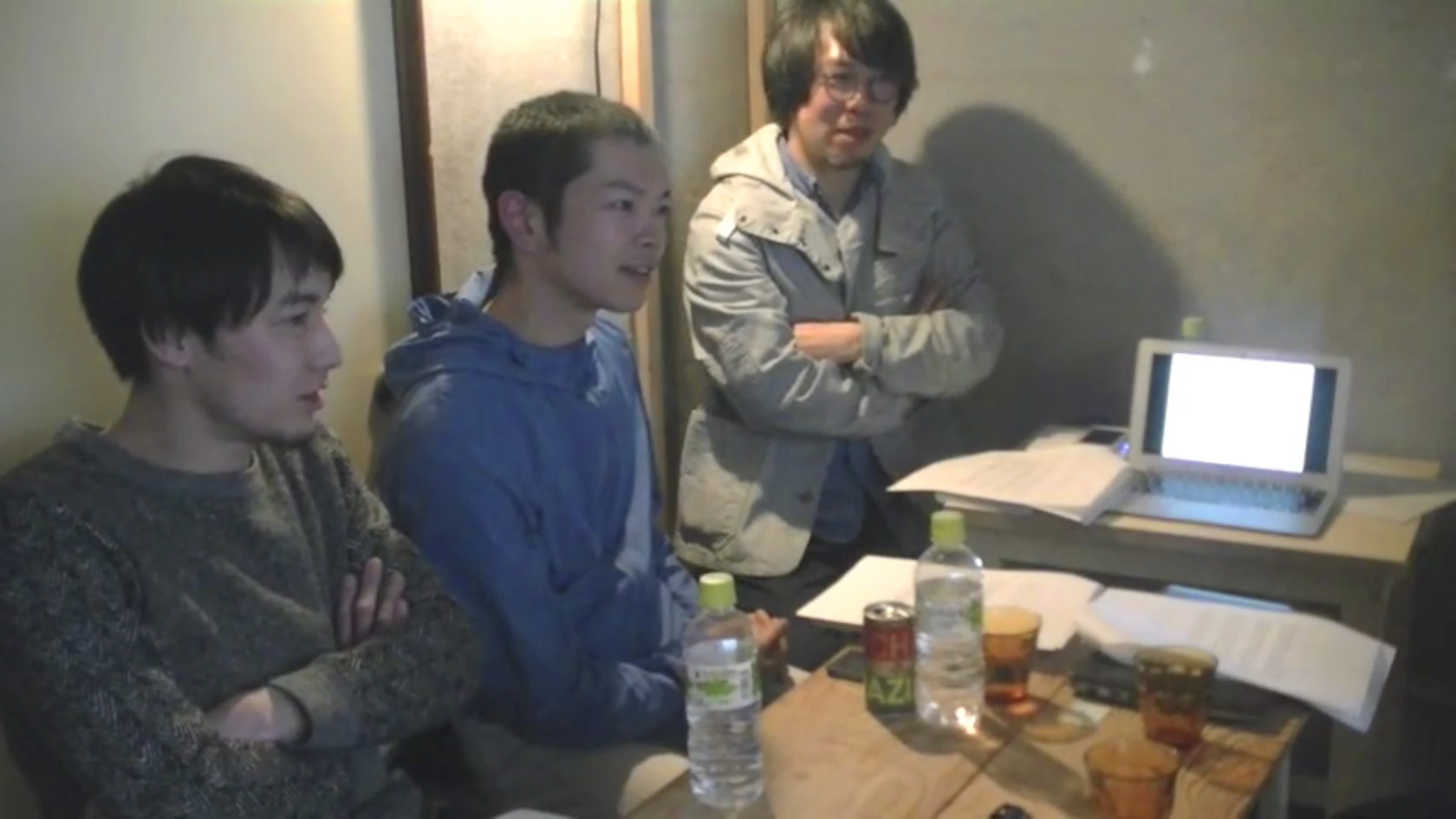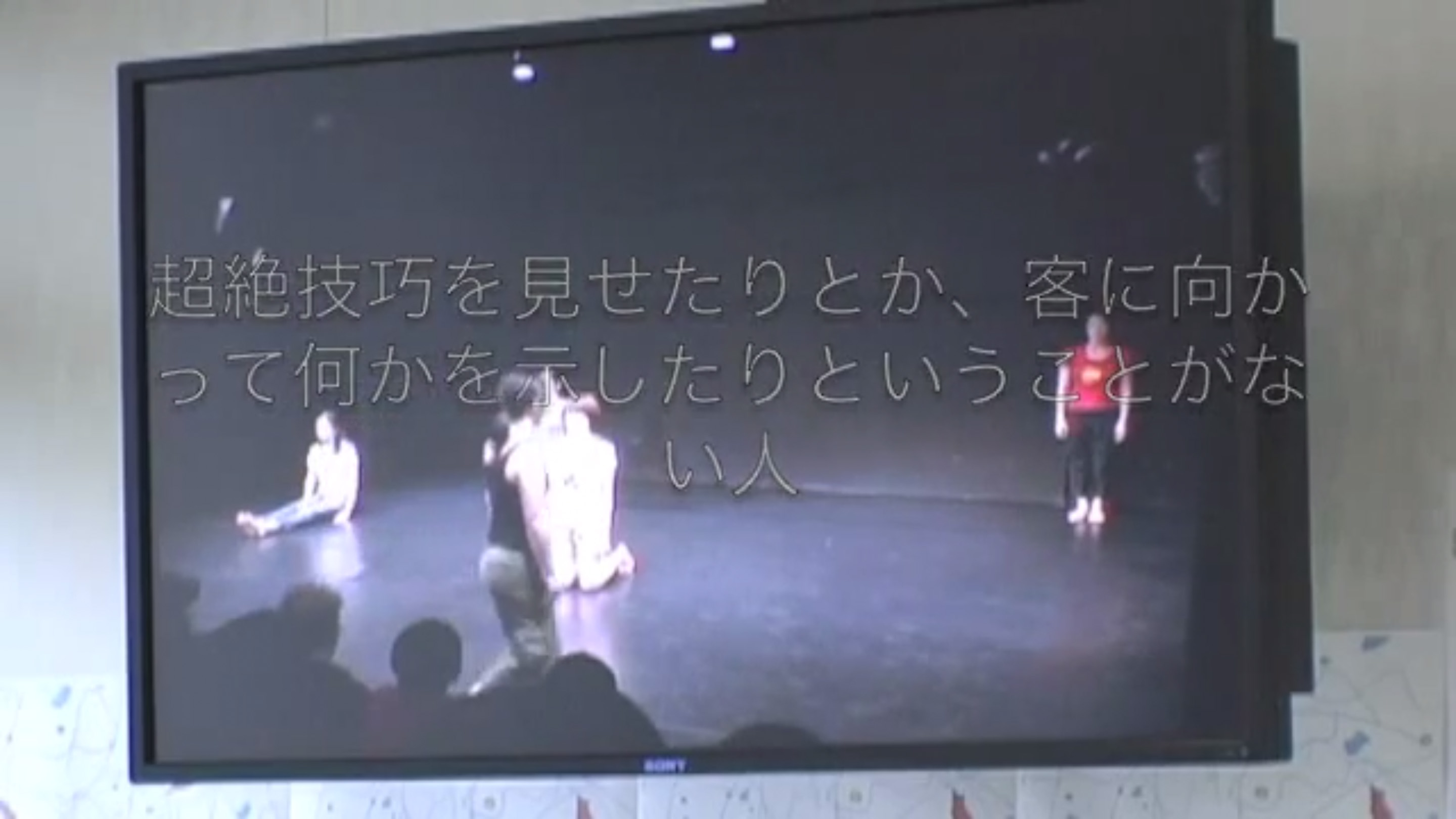2017/09/14
BONUSが「ワークショップ」をテーマに、最初にお会いしたいと思ったのは、堤康彦さんだった。「芸術家と子どもたち」(1999年発足。2001年よりNPO法人)の代表、学校や地域の子どもたちのもとにアーティストを派遣する事業を長年なさってきた堤さん。おそらく私の何百倍も多くの現場を見てきたんだろう。その堤さんから、ワークショップに集う〈学校〉や〈子ども〉や〈アーティスト〉はどう映っているのだろう? そして最良の「ワークショップ」とは一体どんなものなのだろう? そんなことを聞いてみたかった。そして、実際にお会いして、子どもの可能性に静かにワクワクしている堤さんの「眼差し」に惹きつけられてしまった。舞台で自分のアイディアを披露することばかりがダンス作家の仕事ではないのではないか? との思いから「ワークショップ」の未来を模索している私のような人間に、優しく力強い堤さんの「眼差し」は、頼りになる道しるべに見えるのだった。
取材日 2017/2/27(@芸術家と子どもたちの事務所にて)

©仙道美穂子
コーディネートという仕事で起きていること
木村ASIAS(エイジアス: Artist’s Studio In A School)★1というプロジェクトはどんなものですか、またその中で芸術家と子どもたちの方々はどういったお仕事をされているんですか。
- ★1
- ASIAS:http://www.children-art.net/asias/
堤私たちはコーディネー トを行っています。学校や幼稚園・保育園の先生など普段子どもたちのそばにいる大人から依頼が来て、そこから私たちの活動はスタートします。ヒアリングを行い、子どもたちにどういう体験をさせたいのか先生たちの思いを知り、一旦持ち帰って、アーティストを選定し、依頼します。その後、アーティストを交えて三者で細かい打ち合わせをし、ワークショップ本番という流れで進めていきます。先生が何かしらアーティストに期待を抱いている状態があり、その何かというのは先生によって違うんですけど、先生の思いだけだと先生の考えている範疇内になってしまう。その1歩か2歩先を経験できる取り組みにしようと思っています。アーティストが入っていくんですが、面白いことをやってくれそうだなというアーティストに直接声をかけて、先生の思いと調整していきます。ワークショップの最中はアーティストがリードしていきます。我々はあくまでサポートです。
木村学校の先生たちはアーティストに何を求めているのでしょうか?
堤先生の方はアーティストのことを多くは知りません。選定はこちらで行います。マッチングのところが一番大事で、最初の打合せで先生の話を丁寧に伺います。子どもたちの実態も重要です。学級にはどんな子たちがいるのかとか。教室にじっとしていられないような子が2、3人いるよとか教えてもらい、そういう場合アーティストはだれにしようか、ということを考えますね。
木村ワークショップは毎週ある科目の中で行われるんですか。
堤小中学校の場合は正課の授業枠のなかでワークショップを実施します。中学校でも特別支援学級では個別の指導計画になるので、時間割はもちろんあるんですけど、割と自由に時間が取れるんですよね。そもそも中学校の通常級ってなかなか手があがらないんですよ。小学校がメインなんです。一つの要因に中学校の授業が教科担任制で、ダンスや演劇の入る隙がないことがあります。体育でダンスが導入されて、たまに体育の先生から依頼があります。小学校の場合だと、担任の先生が窓口になるので、自由がきく部分があるんです。
木村どんな先生が多いですか?
堤本当に色々ですね。アートが好きという先生もたまにいます。あとはやっぱり子どもたちに色々体験させたいという意欲的な先生が多いです。もちろん、こういうことを実施すれば先生の仕事が増えるわけですが、それでも子どもたちに体験させたいという熱意を持っている先生 が多いですかね。たまに管理職の先生から申し込みが来て、担当になった先生はやらざるを得ない、というケースも無きにしも非ずです。
木村そういう場合は少しやりにくい?
堤最初はそうですね。でもほとんどの先生が子どもにとって良いことだと分かってくると、喜んで取り組んでくれるようになります。

アーティストに求められること
木村先生たちにどうやって今日のアーティストの行う芸術を伝えていくんですか?
堤最初、先生にこちらが授業への思いを聞くわけです。聞いた上で、例えば、ダンスならばこう少し身体を触れ合わせて、言葉ではないコミュニケーションだとか、信頼関係を築いていくというワークがあって、そういうワークを行うアーティストがいますけどって話をしていきますね。先にこっちがこういうのはどうですかというのではなく、先生から話を聞いて、というところからスタートするわけです。とはいっても先生がパンフレットの事例を見て、これを学芸会とか発表会でやりたいと持ち込んでくる先生も非常に多いですね。やりやすいですからね。もう一つは、これはうちのやり方ですけど、ある支援組織から採択を受けて、何校くらい、何日くらいできそうかということが年度で決まってくると、割とうちから特別支援学級の方を誘うんです。特別支援学級に「こういうのはどうですか、アーティストが来る授業はどうですか」という募集をかけています。
木村参加するアーティストとはどのように知り合ってきたのですか?
堤面白そうなアーティストを普段から気にしています。新しいアーティストをどんどんとは増やせないんですけど、新しい若いアーティストにもチャンスがあれば声を掛けようと思っています。
木村オーディションとかはある?
堤そういうのはないです。さっきも言ったように、学校なり相手先の意向からスタートするので、依頼内容やクラスの子どもたちの実態に合わせて選定しています。非常に理解のあるリピーターの先生の場合は新しいアーティストを起用してみようかなとなりますし、子どもも大変だし、先生に対してちゃんと言葉で説明してもらわないとダメだなと思う時はそれに応じたアーティストを連れていきます。登録したアーティストがいるという仕組みではないので、その度毎に声を掛けています。誰を派遣するかはASIASにとって大事なポイントなので、スタッフみんなで話し合いながら行っています。
木村こういうアーティストが良いアーティスト、という分かりやすい答えがあるというわけではないんですね。
堤そうです。個々のアーティストの得意なところと合う現場をお願いするという感じですね。子どものエネルギーにどのくらい対応できるかな、とか。とくに特別支援学級では普段の子どもの様子を見せてもらい、アーティストを決める時の参考にさせてもらっています。
木村デリケートにコーディネーションされているんですね。そこは、作家が成長する場だったり、学ぶ場だったりするんでしょう。こういうシステムが乏しいことを僕は残念に思っています。ワークショップが自分の成長できる場だと思ってワークショップの講師役を担当したいというアーティストがいるとしたら、どんな心構えが必要だと思いますか?
堤まず色んなことに興味を持つってことですね。興味の範囲、視点をズラすってことができることと、とくに子どもの場合かもしれませんが、子どもが何を感じ今どういう状態にあるかを見ようとすることですね。
木村「こういうものを授けよう」とあらかじめ考えること以上に、その場の空気をまずちゃんと理解することが必要なんですね。
堤そうですね。慣れていない内は色々やってみればいいんですよ。時間切れになっちゃったとかそんなことはあっていいんですが、トライしなかったり、子どもをただ型にはめようとしちゃうアーティストは、うちではちょっと厳しいかなと思います。子どもが何を感じているかというのも難しいですけど、アーティストもその場で何を感じるかも難しいと思います。先生の目も気になるし、我々スタッフも居たりするので、それも気になったりするじゃないですか。
木村でもだからこそ良い経験のような気もしますよね。即興的に出てくるものを瞬時に咀嚼できる力というのは、すごく大事な気がします。
堤例えば、あるアーティストの場合、彼は喋るんですけど声が聞こえないんですよ。ぼそぼそと喋るから。だけど案外子どもには伝わっていて、意味は伝わっていないかもしれないけど。別に言葉で喋ることがそんなに重要ではなくて、アーティストが発するものは子どもの方が割と敏感に感じ取るし、やってみて理解していないことは我々がフォローしたりすれば良いので。
木村「子どもを信頼する力」が重要なんですね。

©松本和幸
特別支援学級とワークショップ
木村ところで、なぜ特別支援学級に重点を置いているんですか?
堤最初は通常学級でワークショップをやっていたんですけど、通常学級でも色んな子がいて、いわゆる発達障害の子とか自閉的な傾向の子どもとかがいるという状況を段々知って。そして、そういう子たちがアーティストたちと出会うと面白いことが起きたりというのを見てきました。そこのいくつか面白い──面白いというのは語弊があるかもしれませんけど──、特別支援学級の子どもたちとのプロジェクトは面白いんです。一つは彼らの感覚、感じ方、とくに自閉的な子どもとかはなかなか言葉に発することが難しかったりすることが多いんですが、しかし、空間とか雰囲気とかをちゃんと感じ取っているんです。いわゆる「感覚過敏」の子どもも多くて、感覚過敏で生活が大変ということはもちろんあるんですけど、過敏であると同時に繊細であるというところもあるので、その感じ方、対ヒト、対モノ、対空間とかそういうものに対する感じ方みたいなものに興味があるんです。
木村具体的なエピソードはありますか?
堤例えば、自閉傾向の子についてよく先生方は「やることの見通しが立ってないと不安になる」と言うんですけど、その割に即興的な動きに乗ってくることがあるんです。とはいえ、子どもとアーティストとで一緒にやってみましょうとなった時に、まだ何をやるワークなのか見えないまま一緒にやろうとすると子どもは拒否するんですよ。不安なんでしょう。でも、みんながやっているのを見て、なんとなく分かってくると入ってくる。その感じ方が興味深くて。僕自身も人とあまり触れあうのが得意ではないので、彼らなりの、例えばパニックになったりだとか、それには何か理由があり、理由は分からない場合がほとんどなんですけど、でもそうした子が時々記録を取っている僕に手を触れてきたり、そこで通じ合うことができたり、そういうことが結構あるんです。
木村面白いですね。恐らく、学校側も客観視できず、アーティスト側も自分の仕事に夢中になっている状況で、堤さんのようなスタッフが観察者の立場でその場の微細な出来事を把握しているという部分があるんですね。
堤アーティストは進行しないといけないから、なかなか一対一では見れない。そうするとはずれた子がどんな気持ちでいるのかということはスタッフ側がケアをします。もちろん先生もいらっしゃいますが、先生は子どもを進行している課題の枠にぐいぐいはめようとする場合もあり、そういうやり方で本当に良いのか、別のケアの仕方もあるのではと思うことがあります。
木村息子が小学校一年生なんですが、田村一行さんに夏休みの二日間ワークショップを息子の小学校で実施してもらったんです。その時、あきらかに発達障害とまではいかないまでも、ルールを意に介さない男の子がいて、結構やんちゃに暴れていたんですよ。でもワークショップが終わった後、田村さんから「木村さん、あの子の動きハチャメチャでよかったですよね」と言われたんですよね。僕もそう思ってました。でも学校って枠の中だと、「正常にできないダメな子」だったり、「注意を受ける子」なんですよね。良いのか悪いのかそこもお聞きしたいところなんですけど、芸術のまなざしからすると十分に見ごたえのある身体だったりして、学校のロジックと芸術の目指すポイントととが微妙に重なったり離れたりしながらその場があるんだなと思ったんです。
堤アーティスト側は身体を使って何かやろうとするけれども、従順にその課題(ルール)を守ることが目的ではない。それよりも、何か面白い動きが出てくればそれでOKなので。先生の方は「そうじゃないでしょ」って、違うことをやり始めてしまう子供に言ってしまうんですね。バランスを重んじるというか、本当に「ギャーッ」となっている子を認めてしまうと、今度はできている子の立場がなくなってしまう。
木村その辺りをお聞きしたかったんです。少し調べてゆくと、どうもアーティストに2つのパターンがあるような気がしてきました。一つは、とにかくルールを設定してそのルールにぐいぐい参加者を引きつけていくタイプ。もう一つは何かアイディアを投げかけはするんだけど、ワークショップ参加者が自分でそのアイディアを吟味するのを待っている作家のタイプです。簡単に良し悪しは言えないと思うけど、「ルールを設定し、そのルールに従う参加者は良い」というスタイルは学校で「規律正しいことが大事」と考える思考法とあまり変わらないかもしれないですよね。とは言え、もう一つの、参加者が考えるための余白を与えてくれるワークショップというものは、作家の力量が求められる気がしました。
堤個々の環境や状況によると思うんです。同じアーティストでも周りの先生たちが場の雰囲気を作っていて、子どもたちが互いを牽制し合うとか、その状況によってある程度型にはめたほうが良い場合もあるし、人数が少なくて時間が許されるのであれば、じゃあそっち[後者のスタイル]にみんなで持っていこうよ、と持っていく。アーティストにもよるし、その時の状況にもよるのかなと思いますね。
木村なるほど。1年間に沢山のワークショップを実施していらっしゃいますが、とくに成功した事例ってありますか?
堤例えばですけど、向雲太郎さんに来てもらったことがありました。向さんは非常に真摯に子どもと向き合ってくれるアーティストでした。特別支援学校で、子どもの数も20人ほどで多く、知的や情緒障害のクラスだったんですけど、最後に発表を行うという形のプログラムでした。発表は文化祭なのですが、特別支援学校の多くの場合は生徒の脇に先生が付いてセリフを一緒に覚えて誘導したり、ステージに一緒にいて黒子みたいにすることが多く、どうしても先生が目立ってしまうところがあります。ストーリー等も先生がある程度決めるものと先生方は思っていたり。向さんの場合、即興をやらせる、すると子どもたちは自由気ままに動く、あるいは逆にその場に居る、動かなくて佇んでいるだけ、なんてことになりました。ステージから落ちちゃうんじゃないかとか、先生方は随分不安を感じたみたいでした。向さんはステージに出るんですけど、先生方は最終的には舞台袖の中で子どもたちを見守るだけという形で作品が完成されていきました。向さんは子供たちの様子を見て、子どもたちの存在そのものが非常に魅力的なんだと、そのままで居られるような作品作りをしていきました。それだと保護者が観た時に分かりづらいんだろうな、それでも良いかなって先生たちは心配しました。結果的には保護者たちも自分の子がやらされているのではなくて、自らこうしたい、やりたいと感じてやっているという状況を非常に肯定的に受け止めていたらしいです。後で先生から聞いた話ですが。
木村なかなかすごいですね。
堤アーティストと一緒に過ごすことで、子どもたちのみならず、周りの大人も含めて変わっていくんですね。パーっと動いてしまう子のことを先生たちは「その子たちを常に引っ張っておかないと」という気持ちが強かったんですが、発表の際にステージから階段を降りてどっかに行ってしまうってことはなかったんですよ。袖にはけて出てこないという子もいなかった。みんなで一緒に何かをやりたかったんでしょう。あまり言葉を話さない子たち同士で何か通じ合っているところがあるのかなって感じました。
木村STスポット横浜という法人の活動を、昨年、取材させてもらった時に、テニスコーツという音楽系アーティストが特別支援学校で行ったワークショップのことを聞きました。★2重い障害を持った子どもが多くて、ほとんど動かないし、言葉も発しない。そこで彼らは音楽を奏でたり、色々な装飾物を作っていったんですね。五感にすごく刺激があるパフォーマンスなのですが、テニスコーツの2人は子どもたちがほとんど反応してくれないので、何か子どもたち自身に得るものがあったのかということに、不安を感じたというんですね。このことは、障害の有無に限らず起きることだと思います。子どもたちの“得た”っていう感覚をどういう風にこちらは想像したら良いのでしょう?
- ★2
- BONUS:ジャーナリズム「田中真実さんと考える、教育現場とダンスの接点で いま起きていること」: http://www.bonus.dance/journalism/06/
堤難しいですよね。とくに身体を使ったダンスのようなワークショップの場合は、言葉にすることで何か落っこっちゃう、違う方向に行っちゃうような危険もあって。たぶん頭の中で冷静に言葉にできても、本当の意味で子どもの体に沁みこんでいるのかは分からなくて。特別支援学校の場合はそもそも言葉にすることを求めていない場合が多いので、実際に何を学んだのかは確かに分からない部分がありますが、アーティストは手ごたえみたいなものは感じてるんじゃないかなと思います。あと先生の方は普段から子どもたちと一緒にいるので、普段の様子と今日のワークショップとの様子を比較して、目の輝きや表情とかで読み取っているのかな。
木村素朴な疑問として、子どもたちはそもそもが十分表現力を持っていて、勝手にでたらめに動いていても非常に魅力的です。自分の息子を見ていてもそう思ってしまうことがあります。アーティストが「何かを与える」なんて余計なことのような気もするんですね。素朴な魅力、魂の爆発が起きている場で、振り付けを与えるのは一つの教育であるとは思うんですけど、教育すると消えてしまうものがあるとも思うんです。

©仙道美穂子
ワークショップはアーティストが学ぶ場でもある
堤ワークショップっていうものをどう捉えるかはアーティストによって違うのですが、そこには関係性の問題があると思うんです。アーティスト側ばかりが与える役をしているわけではないですよね。子どもが向かっているものにアーティストが何を感じて、その場でどうそれに応えるか、または応えずそれをじっと見ているか。子どもだけが学んでいるわけではないんです。
木村失敗の事例があるとしたら、アーティストが自分のイメージしたものにあまりにも頑なにこだわってしまったということですかね?
堤それはあります。とっちらかっちゃって何だか時間も分かんなくなって、チャイムが鳴って尻切れトンボみたいになったりとか。でも僕はそのこと自体気にしていないです。先生にもよるんですけど、先生がそれを非常に神経質に気にする場合はマイナスの評価をしてしまう。やっぱり先生の問題は大きくて、その場にいる人、私たちスタッフも含めて、立ち会っている人全員が影響し合えるような場なので、そこは難しいところです。
木村ワークショップって一つの空間に集った人全員が参加者になってしまう場ですよね。
堤それこそある子が騒いであーだこーだ色々動き回っちゃっているけど、たぶんそれでもその子はワークショップに参加したいのに、こうしなさい、ああしなさいと言って先生が参加できなくしているというような場合もある訳です。普段のルールがあるけれども、こういう時間だから気にしないという先生もいれば、普段通りのルールをワークショップの場でも大事にしないといけない、という先生もいます。たがが外れた子どもたちのその後の面倒を見るのが大変と言う先生もいらっしゃいますし。
木村先生の方も冒険なんでしょうね。
堤何でも自由で良いって訳でもないはずです。ある枠組みを設定した方が自分を出せる子どもの方が多いんです。その枠組みをどう作るか。だけど集団でやっているからみんな枠組みの好みが違う。一方、集団でやる良さもあって、お互いに影響し合って、そこをちょうど良いバランスで時間を過ごしていくという。下手に何もしなくても良い時間だったねっていうこともあるし。
木村アーティストにとっても勉強の場っていうか、得るものの多い場なんじゃないでしょうか。つまりアーティストがあるベクトル、若い頃はともかく自分で作品をどうにかしたい、あるいは自分の才能っていうものを確固とした形にしてみたいというように、自分のことにすごく向き合うと思うんですね。でもそのベクトルの間、そこに生きている限りは子どもたちを教えようとは中々ならないですよね。でもその回路を一つ作った時に、明らかにアーティストの成長があるような気がするんですけど。
堤もちろん対子どもというのもそうですけど、先生からの希望とか依頼に基づいてアーティストが行きます。すると、アーティストの今やりたいことと、先生のやりたいこととは、ちょっとというか、大概ずれている訳ですよね。今年の総合的な学習は“環境”で、“水”をテーマにしているから、“水”で何かをやって下さいみたいな、具体的な話が出てきたり。そういうのも含めて、それに対して自分の創作の方向と違うということでアーティストは拒絶したっていいんですけど、それを面白いと思って、ちょっとやってみようかと、今やっていることと水を繋げてみようかなと、そういう機会にはなると思います。
木村BONUSがおせっかいして、アーティストにテーマを渡すやり方と少し似ている気がします。
堤先生なので単純に「え?」っていうようなことも言いますし。アーティストにこれ言うのって。間に立つ我々はそこのバランスを見て、これは先生ができることでアーティストに言うことではないということを切り分けしている。例えば、集合する時に「前へならえ」を言うのはアーティストではなくて、先生ですよね。それをアーティストの方に「どうすれば良いですかね。」と聞くこと自体おかしいじゃないですか。そういうケースはある程度コーディネーターである我々が少し軌道を修正していきます。でも人間なので会って話をすると色々な話が出てきます。とくに1回2回の場合は、お試し的な感じでお互い「よかったですね。」で終わるんですけど、日数が増えてきますと先生も色々言いますし、アーティストの方も言いますし、もちろん子どもたちがどういう子かってどんどん深く分かってきますので、出来る可能性も広がるし、悩むところも深まっていく感じにはなります。
木村芸術家と子どもたちのパンフレットを拝見すると、「ダンス」と言わずにその代わりに「身体表現」と書いてあります。どういった理由があるんですか。
堤別に「ダンス」って言ってもいいんですけど、一般的に使われている「ダンス」というものよりもその前の段階の感覚を知る、例えば、互いの腕の重さを知るとか、そういう部分を明示したかったからです。それを一般的には「ダンス」とは言わないですから、だから「身体表現」という言い方を使っています。

先生と学校と「ダンス」
木村身体表現という芸術の在り方にすごく感化される先生はいますか?
堤リピーターは結構多いんですよ。先生が異動しても別の学校で行うとか。
木村やっぱり先生単位というか先生の熱意によってこの活動が生まれるということがすごく大きいんですね。
堤先程は結構否定的なことを言ってしまいましたけど、やっぱりすごい先生はいらっしゃって。この人はアーティストかっていう感覚の面白い先生もいらっしゃいます。あとやっぱり先生の立場っていうのはまず子供のことを考えているので、子どもを見る目というのはどうなのかって言った時に、今の子どもたちに対して身体の問題というのを非常に重要に考えている先生も実は結構いると思うんです。とくに小学校とか。今の子どもたちの身体を少し心配しているというか。或は身体を動かして自分を表現するということがもっと必要なんじゃないかとか。だけど自分はそれを中々指導することができない。身体を通じた友達との関係性も含めて気づいている先生も実は結構いるんじゃないかなと思っています。それが指導要領の中で明確に謳われてないので、現場にいる先生は子どもたちの身体を気にしている。
木村「ダンスの手前」の話かもしれませんが、でも、それは考えようによっては「コミュニケーションの原型」というべきものかもしれないですよね。それが案外カリキュラムの中では教える場がなかったりすると。
堤体育になるとは思うんですけど。体育はやっぱりどうしても別のベクトルのものでかなり広範囲で構成されているので、その中でそれをやるのは結構難しいかもしれないですよね。身体を強くとか早くとか、できたできないという基準が中心で、その分、身体表現的なことは先生方も苦手なところがあります。
木村そうすると、現時点ではという話かもしれませんが、決まって週に1回身体表現の時間があるって形にはなってはいませんね。そういうことよりは短期集中の1週間とか10日という形で学校を揺さぶる、そういう形が良いんですかね。
堤やるチャンスは見つけようとすれば結構ありますが、中々そこまではいかない。でも、とくに小学校だと授業時間だけではなくて休み時間とか普段の学校生活全体の中で身体をどう捉えるかというのは、先生の方が結構意識しているんじゃないですかね。どっちかっていうと今は言語活動というのが全ての教科の中で重要になってはいます。言葉で表現できない子が多いことを、非常に問題視している先生も多い。自分の気持ちを全然伝えられてないとか、言いたいことが言えてないとか、理路整然と喋れないとか、そういうことが気になっている先生の方は多いですよ。
木村なるほど。言語表現の基になるものが身体表現かもしれないし、「自分を表現する」という時の「自分」に関わるような部分、それは身体の内側から立ち上がってくるものかもしれないけれど、そういうものがちゃんと活発に動いていないから言語表現が乏しいのかもしれませんね。
堤障害のある子とかを見ていると、とくに発語がなかったり言語的な発達が遅れている子を見ると、他の感覚が良かったりするんですよね。触れることに過敏な子もいるし、聴覚が過敏な子だったり、視覚的に空間の捉え方が非常にすごい子がいたり。そういう子を考える時に実は我々もある意味そういう感覚、才能を持っていたけれど、言葉を獲得する中でそれを封じ込めていっているんじゃないのかなって。そこまではちょっと言い過ぎなのかもしれませんけど。やっぱり言葉を獲得するって相当大変なことだと思うんですよ。人類の歴史の中で言うと。言語を獲得した時点で何かが色々封じ込めて中々出せなくなっていって。障害がある子とかを見ているとそういうことをふっと思ったりします。
木村特別支援学級・学校とかはとくにそうかもしれませんけど、実はワークショップを通して色々な人が自分のこれまでの発想や考え方が切り替わっていく、そういう力が発生していくことが、一番実りの多い時間だと僕は思うんですけど、堤さんは実りあるワークショップの状態とはどういうものだと思いますか?
堤僕は別にワークショップをしたい訳ではなくて、そこに参加した子どもたちの一人でもいいから何かちょっとした変化、その変化が良い方向、その良い方向という判断基準も非常に難しいんですけど、その子にとって安心できるというか、よかったと思っても思わなくてもいいんですけど、ちょっとした変化というか、あれば良いなと思っています。それと同時に、関係性に変化があるとか、そこに参加している人と人との関係性、もしくは素材との関係性でも、空間とかものとかの関係性でもいいんですけど、何かちょっと変化が起きるということが、もしかしたらワークショップという手法の場合は起こりやすいのではないかなと思っています。
堤さんが見ている「子供との現場」
木村そもそものお話なんですが、堤さんが子どもに興味を持ったのはどんなきっかけからなんですか?
堤以前していたホールとかギャラリーとかの仕事で展覧会等の企画を行っていた時は観客は大人でしたが、大人じゃ「手遅れ」かなと思って。何かを企画して、そこに来る人たちはすでにアートファンな訳です。その仕組みを何とかしたいなと思っていました。あとは、子どもとの方が楽しいだろうなというぐらいのことなんですけど。きっと大人よりも子どものほうが、僕が面白いと思っているアートが通じるだろうなって。アーティスト自身の魅力というのはその時から感じていて、自分では分からないようなことを考えて日々創作活動をしている。アートというよりはアーティストという、人が面白いだろうなと何となく感じていて。その人と子どもを合わせてみたら面白いだろうなと。
木村今のお話も全くそうなんですが、堤さんの現場を観察される眼差しに、お聞きしながらずっと、興味をそそられています。
堤分からないことが面白いんですよね。この子は何を感じていてどうしてるんだろうとか、分からないし分かりようもないっていう場合があるんだけど。極端な話、障害のある子だと、今居心地が良いと感じているのか、悪いと感じているのか、正反対なんだけど、それがどっちか分からない。
木村完全にパフォーマーとみなして観客の立場から堤さんは子どもたちを観察しているんですね。
堤突拍子もないことを仕掛けてくることもあるんですよね。今まで言葉を一言も発してなかった子が10日間のワークショップの最終日に急に僕に話しかけてきたり。僕と何か絡んだ訳でもないのに。僕のことを何か気にしていたのかなとか思ったり。アーティストがどんなことをやっているのかということも大事なんですけど、段々アーティストが何をやっていてもよくなってきて、子どもがどうこの場を感じ取っているのかということに関心を置いてますね。
木村芸術家と子どもたちの活動のゴールってどんなところに置いていますか?
堤学校などの教育現場でこういうことの大切さみたいなものの理解は広めたいなと思います。やっぱり先生も大変なんですけど、大変なのは大人の都合で、子供を中心に置いたらこういう接し方じゃないよねっていうのも見受けられるので。先生の数が足りない現状などがあり、もちろんその先生のせいとばかり言えないんですが。表現するとかコミュニケーションするっていうことがもう少し教育の現場にあっても良いかなという気持ちももちろんあります。あとは、教育でなく福祉現場になりますが、児童養護施設は社会の問題がぎゅっと詰まった場所です。そういうところでアーティストが何かできるか、ということを試すことは続けたいです。虐待を受けた子供たちの比率が多かったり、障害のある子も多いんですけど、親と暮らしていないことをただ単に否定的に捉えず、施設の良さも捉えていきたいなと思います。