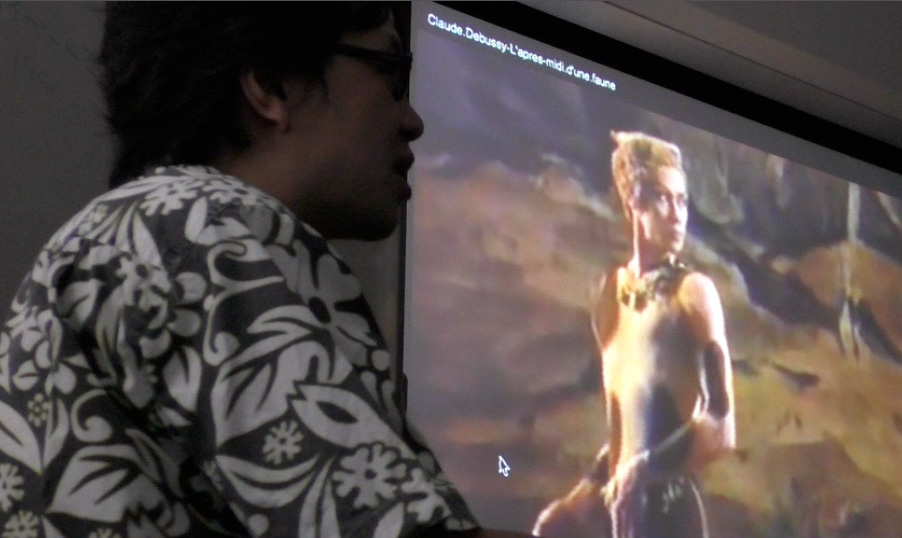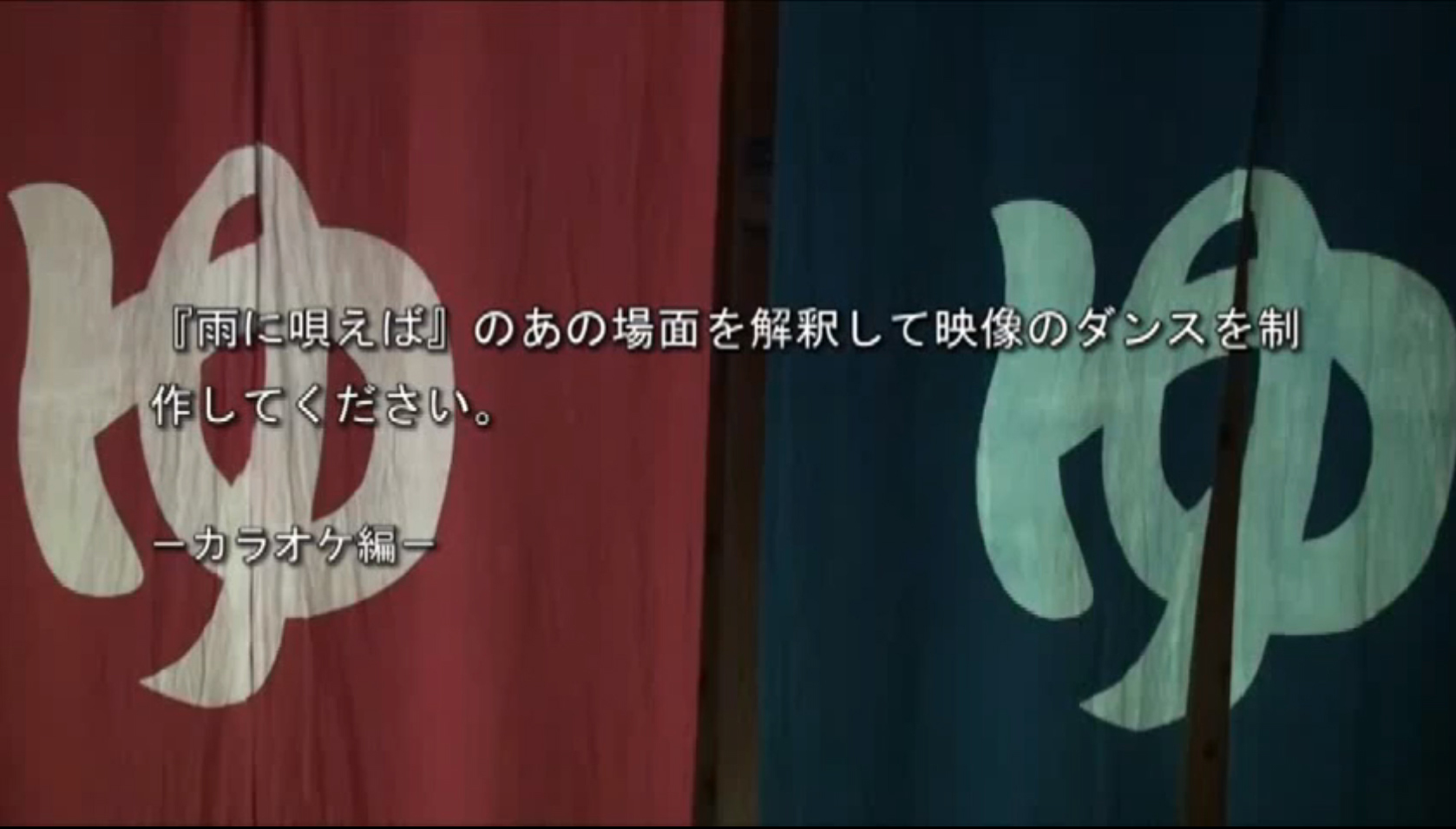2015/04/21
2011年の6月3日と4日、ミュージシャンで批評家の大谷能生と私木村覚とは、舞踏家・室伏鴻の上演を第一部、1時間以上のアフタートークを第二部とした「即興二番」というタイトルのイベントを行った。場所はSNAC。会場は満員となったが、何せ狭い会場、この上演の目撃者は、上演の強烈さ・貴重さに比して決して多いとはいいがたい。
BONUSの第2回連結クリエイションに室伏鴻が参加してくださることになったことに合わせ、2015年の4月、長くSDカードのなかに眠っていたこの2日間の出来事をあらためて目覚めさせ、動画コンテンツとしてこの世にリロードする。
室伏鴻「即興二番」+ ベクトルズ:ベクトルズ・トーク
木村 10日ほど前ですかね? 大谷さんと会って決めたんですよね。なるべくダンスの原理的な話をしようと。せっかくなので室伏さんから聞けることをいろいろと聞こう。それに、室伏さんに触媒となってもらうことで話せることがきっとあるだろうと、期待していました。
室伏 ついこのあいだですよ。2月、横浜のダンスコレクションってあるでしょ? 審査に招かれた時に、まあ、大変だったですよ、ビデオの審査で。私はヨーロッパに居たので、ビデオを向こうで見たんですけど。審査に際して話題になったのが、非常にダンスがつまんないということだった。クリエイティビティが落ちてるんじゃないか、と。で、その、コンペティションだからさ、でその時にね、大学に、ダンスの学科がある大学がありますね、結構。玉川大学とか。岩渕貞太君の母校。複数あるみたいで。私が学生時代そんな学科は無かったにも関わらず、昔からお茶の水はあるよね? で、木村さんは日本女子大学に勤務しているって話を聞いたから。
木村 日本女子大学はダンスを踊る場でもないし学ぶ場でも基本的にはないです。ぼくがいるからダンスの科目があるというだけで。ぼくはだから、ダンスアカデミズムみたいなものの外側とは言えないけれども、そういうダンスの教育機関とはかなり違う場所で、自分で活動しているわけです。その話はちょっと気になるのですが、でも、大学批判してても面白くないので、横浜ダンスコレクションで、80組ですか? ダンスを見たわけじゃないですか。で、不満だった? 面白かった? どっちでしょう。
室伏 面白いものもありましたよ。ビデオでね、私がセレクションするわけじゃないから、落とされちゃったのね、私が面白いと思ったものは。
大谷 ビデオで落とされちゃったんですか?
室伏 〔この年賞を受賞した〕捩子ぴじん君はね、みんなが知ってた作品だし、そういう意味で鮮度は無かったわけよ。で、結局彼になっちゃったんですけど。こういう話しに来たんじゃないんだけど。私が聞いたのは、つまり大学でね、教育として行われるダンスのことを話題にしたくて。(横浜ダンスコレクションに応募してきた振付家は)みんな個人差があったね。それをコンペティションにかけてね、「こいつがナンバーワンのアーティストだ」って言われる、というようなことはある意味でおかしいんじゃないか、と。で、そういうこともわきまえた上でだね、乱暴にものを作っているやつがいるかっていうと、みんなちんまりおさまっているわけですよ。ある意味、ダンスを信仰しているのか知らないけれども、ダンスは踊ることだと思っているみたいなんだね。それで私がなんでわざわざ審査に招かれてね……。つまり「踊らない」っていう問題ですね。「踊る」っていうことのなかに、ある「恥ずかしさ」っていうものが絶対あるわけで。それがいわゆる「クリエイティビティ」の本質に近いんですよね。だからその「恥ずかしさ」っていうのは非常に難しいんですけども、非常に深いところで、いろんなアイデンティティのなんていうか、暗い部分に触れるわけですね。で、そこには何か「闇」があるのか、それともそこには「何もない」のか。そこに触れていかないと、いい作品はできないわな、っていうようなところまで突っ込んで話はしなかったですけど。
木村 そこでは。今日は、その話しましょう。
大谷 そこでこそするべき話なんじゃないですかね。ここでやらなくてもいい気がしますけど。聞きますけど、そういうことを聞かれなかったんですね?
室伏 いや、だから、当然コンテンポラリーダンスっていう「同時代性(コンテンポラリー)」ということでいえば、ダンスが終わった地点からはじめる、私はある意味そういうことを考えている人間だと認識された上で審査に呼ばれてるっていうつもりだったんだけど、むしろそうじゃなくて、その踊ること、まだ信仰してること、ある種の表現っていうもののね、疑いもなくそれを表現する人たちがいて、それは非常に〔…〕。
木村 でも根本的な問題ですよね。ダンスは教えられるのか否か、とか、ダンスっていうのはどこにあるのか、とか。今日は、そういう問題をいろいろと考えさせられる舞台だったように思うのですけども。大谷さんどうでしたか?
大谷 考えさせられましたよ。DJがね、とにかく。いきなりだけど、何ていうか、動いてるものに音をのせると、合っている、またはくっついたり離れたり勝手に逃げちゃう、というか聞こえちゃうというか。よく知ってることなんですけれども、要するに、合ってればいいわけでもないし、ずれてればいいわけでも全くないわけで、ある種のその〔…〕スピード感というか行ったり戻ったりっていうか、「恥ずかしさ」という言葉が出ましたけれども、「そんなに簡単にお話しは進めさせないぞ」みたいな、「嫌がらせ」じゃないですけども、スムーズにいったらきれいに終わるところを、止めたり、とばしたりするっていう感覚はすごくある感覚なので、こういう話をやる前にあらかじめしたわけじゃないですが、とにかく室伏さんのダンスを今まで見てきて、とてもひっかかりがあったんです。ドッキングとでもいいましょうか、クラッチが上手くこう、スムーズに上手くこう加速してくのかなと思ったら、ガリガリガリッ! みたいな感じで止まっちゃう、止まっちゃうっていうよりなんですかね。空転じゃないですけど、なにかしらその空転、ギア比があってない時みたいな。ものすごくエンジンが回ってるんだけど、ギアがすかすかになってるとか、またはもう完全に入れ損なってる状態を執拗に行っているみたいな感じは知っていたし、好きなところだった。で、なんかお客さんには悪いなと思いつつ、ぐちゃぐちゃにしちゃったみたいな感じがちょっと。
木村 大谷さんにちょっと聞きたかったのはその話になったらこのことを聞こうかなと思ってたのは、その最後の最後の最後のほうで、室伏さんが転倒するじゃないですか。そこに音っていうのをどういう風に沿わせていくかというか、からんでいくのかっていうのは、聞きながらいろいろ感じたんですけど、結構難しかったんじゃないですか? 見ながら少しこうエフェクトしていく感じ、作っていくって感じ?
大谷 ああ、えーと、ちょっと上手く行きませんでした。
木村 どんな感じだったんですか?
大谷 えーとね、要するに、これ、音楽用語で「ふるえる」っていうんですけど、最後の方だけ結局やったんですけど、どっから入っていいのかちょっと分からなくなっちゃった。
木村 倒れた時?
大谷 いやいや、逆立ちする時。
木村 逆立ちする時?
大谷 いや、あとどこから、その、相当緊張感のあるものなので、音楽も情報量増やすと見る人がうぜえかなって思って、その場は最後までするっといっちゃって、あとは全部室伏さんに任せるかなって思ったんですけど、曲が終わりそうになっちゃったんで、あとこれ3分くらいやりたいなって思ってしまって、勝手に。で、カット始めたって感じだったんで、木村さんが今言われてるような余裕は全くなかったんで、明日のほうが上手くできると思います。
〔中略〕
大谷 今日こうだったんですよね。室伏さんじゃあ明日はこうですかっていうような話を、聞きたいっていう感じ。ですよね。
木村 でもね、その、室伏さんの公演を見ていて、いつも気がかりなのはその、音というパートのことで。印象的な曲とか、音とかっていうのが差し挟まれているんですね、全体の三分の一、いや、四分の一ぐらいとか。でも、ぼくは、音の無い時間こそ集中的に見ることができるという感じがあるんです。反対に、音が、音楽が流れた瞬間に、舞台がある種の方向に一元化されてしまうような気がするんです。さっきのあの大谷さんの言い方の「空転」で言うと、ぼくは、あの、色んな可能性をはらみながら、さあ、どこに行くんだろう。室伏さんの胸の内、今どこにあるんだろうって思う瞬間というのに、もうわくわくさせられてしまうんですよね。そこに惹きつけられる。それが、音楽が流れはじめると感情が一方向に限定されていってしまう気がして、そうなるといつもさびしいような気持ちなるんですよ。そのあたり、音楽って室伏さんはどういう風に音について考えているんですか?
室伏 いま、大谷さんが言った「空転」ってのは、ずれじゃなくて〔…〕コラボレーションできることは、最初から決められていてってわけじゃないんですよね、ブレイクしながら、だからそういうことでいうと、最初のそのアカデミズムダンス批判じゃないですけども、全部最初から踏み外してるっていう風に思うんですよ。舞踏っていうのはそこがいいとこで。舞踏があらわれて50年以上か。その、なんていうんですかね、余波っていうか影響たるや、インターナショナルですよ。日本のなかでは、最初っから日陰者だったんだけども。「日陰者ってなんぞや?」っていう問い直しのきっかけになるようなものになればいいと思うんですけどね、舞踏って。
木村 日陰者が、でもある時「日陰者」っていうダンスのジャンルが出来上がって、で、そのメソッドが確立されて、それを全然日陰者じゃないエリートが学ぶみたいな、なんかこう転倒した状況が起きがちですよね?
室伏 スタイルとか様式っていうのが、フォルムっていう問題の捉え方っていうのが根本的に問題含みなんですね。「過ぎ去っていくもの」をフォルムって規定する人もいるわけですよね。「動いていくもの」をフォルムだっていうのを規定した場合に、「形」って言葉、土方さん使ってるけれども、命と形のせめぎ合いとか言うわけですよ。ところが、命のなかに形があってね、命と形のせめぎ合いっていうのはひとつの体の中で行われてるから、止めようがない。でそれに話をからめると、情景ができちゃうわけですよね? その情景を駆使するのがシアターですよ。その時に、ある種の、一番後ろにいるのは危険性ですよ。その場で生成していくっていうのは、ビカミング、成る、っていう。その場で成立していくっていうのは、舞台でいくら私がスケッチしておいても、お客さん次第でね。このスペース(SNAC)に関しても、私ははじめてですよね?
木村 2回目、かな?
室伏 2回目?
木村 去年の夏に真っ暗闇で踊ったじゃないですか。
室伏 でも、こういうものを今日置かせて頂いたのは偶発的なことなんですね。昨日これ決めたわけで。これに合わせてこれはあるわけでしょ? イベントっていうことはさあ。
木村 今の室伏さんの話で面白いなと思うのは、その出来事とかイベント、事件っていうのは、一人のダンサーがあらかじめ思い描いていたストーリーをダンサー自身が語っているときには実はあまり起きなくて、起きるとすれば、観客との共犯関係の中、観客との間でこそ出来事とか、事件とかは起きると思うんですね。そこで聞きたいのですが、室伏さんはお客さんを踊りながらどういう風に意識してるんですか?
室伏 どう言ったらいいだろう。それは今くっきりね、ステージにダンサーと客席っていうのは二分できるものじゃないって思うんですよね。予定して今日あそこでずっと待ってたんですけど、すでにお客さん入ってきてるわけ、土足で、私の中に。だからそういう意味ではお客さんの中にすでに私はもう居て、実際この現場に今日40人か、座って頂いたんですけども、そのお客さんとまた出会うっていうことはなんか二重化されてるような気がするのね。だから単に「間(あいだ)」ってのを、間がどんどんこう増殖してるんで。舞台から落っこちたりしましたけれども、リハーサルで既に一回やってるわけですよ。全然違うやり方で。それは、一番最前列にね、座ってるお客さんみたいのを想定しつつ、だけど本番でやるかどうか分からないわけですよ。だけど実際やっちゃいましたけどね、全然違うタイミングでやったんですけど。
大谷 その時に、じゃあその、あちらで室伏さんが待たれていた時に観客が入ってくるとき、まず、物音が聞こえてきますよね? 見えていなくても。で、いろいろ照明が変わったりとかあって、舞台から落ちる時でも、最前列を意識したりとか遠くを意識したりとか、そういう時に、お客との関係に間ができる、その時に、観客との関係が逐一変わるっていうことが起きるわけですよね。踊ってる最中、自分がやってることと見てる人との間の関係性というのは常に変わるわけですよね。
室伏 そう。そうだと思う。木村さんが言ったその「間」に出来事が成立する。
大谷 その時に不思議っていうか、いろいろダンスを見ていて思うのはですね、間性っていうのをどういう風に設定してるのかっていうことがよく分からない人も多い。間が最初から無いっていう、舞台に上がったらそのまま自分の振り付けをやって、「自分はこうやりました」っていう人は、誰との間にも間が無いっていう気がしますね。
木村 例えば振り付けが、あらかじめかっちりあった状態で、その振り付けを自分が思う完成度のもとで再演するとそれが上演になったって思うような形のダンサーなり振付家の場合は、いま室伏さんが話してくれたような「間」っていうのが省かれた状態で上演されてしまう可能性があるんじゃないかと思うわけです。そういうことって、すごく危ういって思うんですけど。
室伏 それはダメだったことだよな。むしろ「危うい」っていう言葉はすごい大事だと思うんだけども……。ある表現の再現性っていうんですか? それは問題ある気が……。
大谷 まあ、今いわれてることは19世紀までさかのぼることになると思うんですけど。再現性が高い方がいい作品だっていわれている時代が長かったのね、そういうことでいうと。儀式として同じことを何回も出来ないと儀式性が低い、儀式性という言い方もおかしいですけども、なにかを支えるために何回も同じものを正月にやってみせるとか、そういう必要性があったものが、儀式から芸術になっていってなにかしらフレーミングされて、これをちゃんとやることだけが正しいことなんだっていう時代も長かったわけですけども、我々はもうそういうのは見たくない、見たいのかな? どうなんだろう……。ダンスのことでぼくはよく思うんですけども、やっぱり、音楽は、特に西洋クラシック音楽は基礎単位がしっかり詰められちゃってる、12平均律、記譜法、その組み合わせでストラクチャーを作ることが多くなってるんですけども。そういうものにモダン以降のダンス、基礎的なものを発見するのは難しかったからこそ、すごく逆に再現性、間性っていうか、その場で動いていって消えるものに向かうっていうのがすごく遅かったんじゃないかっていう気がしてるんですが。音楽は決められたのがあるから、逆にそれは無しにして自由にやっていい〔…〕っというダンスにおけるその決められたことを〔…〕根強い感じっていうのを〔…〕
室伏 そうだねえ。そういうのって私あんまり勉強してないんですけど。
大谷 いや、即興でやるっていうのを、例えばコンポーズピースもあると思うんですけども、その時にコンポーズっていうのをお客とのあいだの、またはそこにあるものとのあいだのトライアルを、振り付けというか、ある種の、人に教えて、再現できる作品としてやる時にどういったことをまず意識してられるのかな。と。
室伏 まあ、それ最初にいった、ダンスに対して(アンチダンスって言っていいか分からないけども)成立したものを、どこでね、一応ね、〔…〕合う、衝動的には合う、〔…〕アートも商業だからね今や、今やっていうか最初からそうなんだけどね、〔…〕ある両義性を持たせる〔…〕二重性って言って、まあ裏切りですよね。だから自分がダンスを信じてるのか〔…〕そういうバランスの中で成立していけば何かの批評性が成立していくのでね、土方巽の最初はね、最初はそっから成立してたと思うんですよね。で、その、私は舞踏っていうものの問題性は日本のダンスの歴史で重要なね、ある種革命でもあるでしょ? 革命だっていいたいのは、批評性に関してはヨーロッパでもそういったことやったり、アメリカでもね〔…〕さっきいったフォルムにからんでくるんですよね。スタイルが〔…〕ところもあるわけ。
木村 で、フォルムってことをさっきの観客とのあいだみたいな話に置き換えるとね、その動きの形とか、動いて流れていく形が、記号的にはっきり分かり、そしてそれの読み方まではっきり伝えられる時に、もう読まなくてもいいと思ったりとか、あ、そういうこと見せたいのねって。で、その記号をただ読み取らせる、なぞらせるだけみたいな読解っていうのが観客に求められるみたいなステージっていうのがあったとして、それはすごくつまらないと思うんですよね。そうすると、その動きが一体どう転がるんだ、とか、どう流れてくのか、どう受け止めると、いま室伏鴻というダンサーが踊っているその思考とか次の出来事に向かう筋肉の動きに追いつけるのか、そこにはらはらする、っていうことがあると思うんですね。だからその形っていう時に何かはっきりもう客観的に分かるってことじゃなくて、その形自体がすごく、見る者とパフォーマーとのあいだに緊張を含んでいる気がするんですよ。そこがいつも面白くて、例えば最初の方で室伏さんが白いマスクみたいなものをかぶっていて、まず目がどこを見ているのかよく分からない。よく分からないので想像するわけですよ、見る側は。そうすると、どこを見てるのかとも思うし、どんな表情をしてるのかとも思うし、つーっと左から右へ顔をパーンしていく時に一体それは何を意味しているのかとか思うんですね。結局結論は全然出ない。出ない結論を、結論が出ないその状態に何かすごく豊かな、室伏さんが好きな言葉の「成る」っていうことの、なにかこう、感覚をぼくはね、もつんですよね。あるいはその立って、前半の方でこのがれきみたいなものを足でこうさわってるというか押している時に、この音とかこの動きが、形が、一体なになのかっていうともうなんか複数の回答がばーっと出るわけですよね。まあ、それは、震災のこととかも思ってしまいますし。でもそれだけじゃないだろ? とか思うみたいな。すごくそこで、パフォーマーと見る者との駆け引きが含まれていて、駆け引きそのものがもう形っていうその言い回しの中に含まれてるような気がするんだよね。
室伏 それを、間性、っていう風にいいたいんでしょ?
木村 うん。で、そのことをぼくは少し大胆に言うと、室伏鴻パフォーマンスの中には強く感じられるんだけども、それ以外のパフォーマーの中でなかなか感じられない。だから室伏さんが3年ここで踊らない、日本ではっきりとしたパフォーマンス、上演をしてくれない、5年とか、なるとぼくはその感覚をどんどん失ってくんですよね。困るんですよ。やってくれと。で、今回ぼくはこういう場を作りたかった。
室伏 どうなんだろう〔…〕でも、そのダンスのあいだってのは引き受けざるを得ない、でしょ?
大谷 だと思うんですけども、木村さんはいろんなダンスを見てそれを感じないってことですよね?
木村 だから、その、読み取りの空転っていうのを、こちらの見る側の快楽として感じさせてくれるようなダンサーとかパフォーマンスっていうのは極めて少ない気がするんですよね。で、このフラストレーションと、あと、この、室伏さんには、室伏体験において感じるこの感覚を、ぼくしか持ってないのかなあと思うと、大谷さんと話すと大谷さんもツーカーで分かるんですよ。だから例えば音楽の中にはあるのかもしれない。
大谷 音楽の中にはあるの?
木村 うん。でも、ダンスの、例えば大谷さんは何人かのコレオグラファーとか、何人かのダンサーと、音楽と、関わりながら、関わってくれてるわけでしょ? やっぱりそういう中で、なかなかそういうあの、通じない感じってあるでしょ?
大谷 テーマとしてそこを中心には考えてはいないなっていう人の方が恐らく多いかもしれない。でも、ぼくが一緒にやってる人の中で面白くないなって思った人は一人もいないんで、いなかったんですけども。さっきの話で一番最初に室伏さんが言ってた恥ずかしさ? っていうシャイネスなのか分からないけど、ステージ上、特別な空間の中でやって見せる人を見ているっていうその関係性のもちかた自体が恥ずかしいっていうところに消すための装置がステージだったり音楽だったりしますよね。
室伏 恥ずかしさを消すのか。
大谷 恥ずかしさを消して自分が、恥ずかしいのは抱えておいて、見せないというか。極端に言うと、自分でも気が付かない、っていう状態に振り付けだったり、音楽をかぶせる時に、そういう方向になるべく自分のいやな、どうにもひっぺがさないところにはなるべく、フォルムじゃないですけども、出てこないようなものが多いと思う。作品、ダンスとか見てると。そうするとこちらは結構、なんだろうな、頑張って見る、っていうような感じになっちゃうんですけれども。恥ずかしさ、室伏さんが途中で止まっちゃうとか、しゃべっちゃう、とか、やっぱり目の前で見ると衝撃的なんですけども、何をやってるんですか、っていう感じのものとかってある
木村 最初、えっ、っていう感じでしょ。なんかお客さんも、しばらくたって慣れてくるみたいな、笑うこともできないみたいな。
大谷 ぼくも見てて恥ずかしくなってくる、自分も。恥ずかしいっていうのは室伏さんが照れてやってるっていうわけじゃなくて、何かしら自分の鑑賞姿勢を批判されてるような、すみませんでしたって、油断してた、って、しまった、って思って汗が出てきたんですけど。
木村 そういう、観客をそういう風に揺さぶろうっていうのはあるんですかね。つまり揺さぶられないままだと、観客も観客で、あいだを消そうみたいな発想はあると思うんですよ、なんだろうな、ここにあるのは完全なパフォーマンスで、例えばテレビのよく編集されたプログラムみたいなものを、だまって鑑賞するのが鑑賞体験だ、みたいに思っているとしたら、そういうところで、誤訳というかね、しゃべるみたいなことが起きるとなんか全然予定していたことと違う、ってことは自分が思い描いていた鑑賞体験みたいなことが崩壊する。
大谷 油断してたやばい、そんな、指がとれないなんてそんなばかな! という。しまったそんなことが起きてるとは。という。すごくこうやって見てたなっていう。
室伏 別にこういうことやろうと思ってやってたわけじゃないですよ。
大谷 ほんとに、びっくりしましたもん。なんで、距離ががつんと揺さぶられてたんですよね。そういう、先ほどの、お客さんもその共犯関係、あいだ、あるよっていうのを。
室伏 私が真面目にね、そういう指を入れて。
大谷 しかも中指ですよね、薬指じゃなくて。薬指でやってましたけど、これ中指ですよ。室伏さん、それ中指、って思った、っていう。
室伏 ほんとだ。
大谷 ほんとだじゃなくて。
室伏 薬指の方がいいだろうと思ってたんだけど、
大谷 薬指だって言ってるから、どこまでがあれなんだか分からない
室伏 だから、恥ずかしいんですけど、穴に差し込むっていう〔…〕恥ずかしさが多重化されていくでしょ、そこに集中してコンセントレーションして、ある種のダンス性みたいなのを乗り越えていくっていうか、行為そのものを純化していくようなさ、その、方向があるんですよ、もちろん。そういうことに対して、また恥ずかしいっていう繰り返しがあるから、これはもう一緒になって恥ずかしくなった方がいい、いいというような投げかけなんだろうね一応。だけどそれであんまりやり過ぎると笑いみたいなのもあるから、そこの手前で引き受けないといけないなと思いつつやってるんですよ。だけどその、ステージをはがしていく作業にしてもね〔…〕予定外のことなの、やろうとしてたことじゃないの。そのある流れまできた時に〔…〕掘らなきゃいけないっていう、そういう流れが出来てきたよね、だからそれは踊りながら考えてることなので、そういうのは。
木村 そのだから流れっていうのが、まさに室伏さんのその一つの体がというか一つの意思が作ってるんじゃなくて、場自体がその次にここにこうしてこう剥がすっていうところに至らざるを得ないような、そういうこう切迫感というか、思いにかられてしまっていくわけでしょ? それに従って流れていく。
室伏 だからお客さんありがとうってことになるんですけれど。
大谷 例えば、Ko & Edgeなどで人にやらせるっていう場合、どういったことをどのように教えるんですか?
室伏 教えるっていう意味では、十分教えていないけども。Ko & Edgeでいくつかやりましたけども、十分満足はしてないよ。自分が、十全に何かできたのかって言えばね。
大谷 ダンサーがいて、ダンサーとダンスっていうのはイコールではない、往々にしてダンサーが踊ってる、その人のダンス作品っていう形でかなり密着してると。室伏さんの作品は室伏さんと切り離せないと。という発想もあると思うんですが、室伏さんが〔…〕即興でもない形で、〔…〕ダンスとして人に与えて、ある程度のトレーニング、ノウハウをやると、例えば今言ったような、あいだ性であるとか、シャイネスをどう消さないっていう〔…〕どう関係をとるかっていうことを、ダンスとして振り付けできるっていう可能性は今のところありますか? どのようにお考えですか?
室伏 だからそれは、彼らにある種のダンサー〔…〕みたいな〔…〕最初から〔…〕じゃないんですよ。作品をどうしても、一つの作品として提示しなきゃいけないという風になる、形にしていく。そうするとこことここ〔…〕最低限決めておいて、あとは即興〔…〕みたいなものとか、私今日逆立ちしましたけど、逆立ちの作品もあるでしょ〔「DEAD」のこと〕。〔…〕彼らの個性をさあ、つまり排除する、〔…〕それぞれの頑張りを〔…〕それはおかしいはずなんですよね。〔…〕それ以上のことを要求する必要はないわけ〔…〕おりてきた時に声の掛け合いみたいなことをやらせるんですけど、声じゃなくてもいいわけですよ。息でもいいわけですよ〔…〕3人がやりあっていくうちに、いい日もあればすごく悪い日もあるっていう〔…〕だめだったとかさ、それは3人の即興演奏ですよ、〔…〕立ってきて、倒れたんですよ、それはまあ、木村君がさっき言った〔…〕風景が出来上がる。風景を叩き割るみたいな〔…〕倒れるだけみたいな作品なんですけど、あれは、そういう意味の、自発的即興じゃないよね。
木村 なんか、一つ、だから、ぼくはついついそれをタスクとか言いたくなっちゃうんですけど、なんかある一定の設定というか、これをやれっていう課題みたいなことだけがあって、で、そこでさっきの室伏さんの言葉で言うと「頑張る」っていう。それで、頑張る、っていう。そうなるとなにが出るかっていうと、本人が出る。本人が出るってところでなにかこう際立つっていうか、なんかそういう話のように聞こえたんですけどね。なんかそういうやり方なのかな。室伏さんが自分で踊る時とはかなり違うと思うけれども。
室伏 〔…〕逆立ちで踊る、目黒君とか鈴木君とか〔…〕やっぱり見たいっていうのはあるわけ。で、でも彼らの個性ではないんだよね。だからそこが〔…〕当然あるわけ。〔…〕その生き方が体一つでね〔…〕。
木村 シンプルな、なにかこう逆立ちというか反転するという課題を通して生きてるって状態が際立つ。そこを見たい。ちょっと話ずれちゃうんですけど、「美貌の青空」っていう作品の中で、若手の3人が、鈴木ユキオ君と目黒大路君と、あと、林君が、裸で立ってて、3人が近づいて立ってて、両側の2人だったかな、が、指をこう、だすのね。出して、最終的にはこれは、目黒君の乳首に両方それぞれ指がいくっていう話で、でもその指が宙に浮く瞬間に、「はて?」と思うわけですよ。さっきの話をもう一回言うみたいなことになるんですけど、この指はどこへ? って思うのね。いろんな可能性がある。泳いだ瞬間にいろんな可能性に、もう、気が気じゃないわけですね。で、まさかそこでは、って思うそこに、すーって行くので、あーっ、って思うわけですよ。で、なんか3人が、こう、なよってするというので、はーっていうという、あれはね、だから振り付けとして、特にその、指、っていうのが泳ぐっていう瞬間を室伏さんが設定した時に室伏さんがそのソロの即興で今話したような形でやろうとしたことを振り付け化したのかな。という風に昨日ビデオを見直していてそんなこと思ったんですけど、どうなんですか? そんな意図はあったんですか? あの指は観客にとって、そういう複数の可能性を読み取らせてしまう、しめしめみたいな。危ういっていう。
室伏 そりゃそうでしょ?
木村 ですよね? だからその仕掛けがやっぱり面白いなと。そういう仕掛けを、なかなか見れない。という気がする。
室伏 あれはまあね、男同士が乳首をつまみあってるのが、かわいいよね。それがねらいだったから。その前に、あの真鍮板をがんがんがんがん床に叩きつけてかついだりしてる、その硬いもののあとだから、〔…〕きっかけが〔…〕2人じゃなくて3人でやるのがミソだったよね。
木村 そういう意味では、振り付けの中にいろいろな仕掛けを仕込めるような気もするんですよね。爆弾を入れておいて、それがちゃんと時限発火して、ぼんっといけばいい、という。なんかそういう仕方での振り付けの可能性っていうのはあるだろう。だからそのなかでいつも思うのは、つまり観客っていうものとの関係を設定するような動きとか、指さす、とかいう時に、ぼくたちはそういうようなことを勝手に起こしてしまうわけですよね。なんかそういうことを実は室伏さんはいろいろもう当然なんでしょうけど、意識してあらゆる角度からなにが、そこから見るとなにが起きるのかっていうことが、なんかこう、常に計算されながらというか、室伏さんのなかで読み込みながら自分の身体が動いているっていうそういうようなことがあるんじゃないかなあという。ただ、そういうそのある種それはだから最初にそのはじまる前に既に観客は中に入っているという話みたいに、観客ってものがいかに設定されてるか、というのはかなり重要で、同時に観客は室伏さんを自分の中に勝手に設定しちゃうわけですよね。それはもちろんいつもずれているんだけど、でも、それをいかに設定させるかっていうのかな、危ういものとして設定するのかっていうのが重要なんですよね。
大谷 ダンサーは自分が踊ってる体には直接入れないわけですよね。なんで、必ずお客さんというか見る人がいて、その人がどう思ってるのかっていうのを反映させなければ自分がなにやってるのかっていうのが生まれない、ってことですよね。直接、まあ鏡をみるのもあれですけど、なにかやってる自分の行為自体を見れない。
室伏 まあ、反射ですよね。
大谷 反射を助けにおく。例えば、ステージ、客席、と分けちゃって、完全にあっちは自分の思ってることを受け止めてくれる人っていう風にしちゃうと楽ですよね。作品つくる時にそれやんないと多分つくれないということがあるのかなあ。
室伏 〔…〕でも、そのあいだこっちが一歩踏み出したら向こうが受けるわけだから、〔…〕その時に例えば〔…〕あるいはマテリアルだったり。
大谷 なんですけども、そうか、そうですよね。そういう不安、要するに自分のやっていることは自分で見れないっていうのは結構不安定じゃないですか、不安っていうか当たり前ですけど。音楽は割と自分がやっているものは自分で一応聞けるんですよね。そこに関する不安定さはたぶんダンスよりは薄いかもしれないな。たぶん聞いてる人と同じものを聞いてること自体に関しては音楽はそこは少ない。そういう不安定さは。ダンサーが抱えてる〔…〕恥ずかしさみたいなものは、結局誰かに見てもらわなければ成立しないからっていう、どう考えているのかなっていうことに関係するのかな。
木村 なんかね、あと、大谷さんと前にミーティングした時に話したことが、画家だったらキャンバスがあるんで、そのキャンバスを前に自分をお客さん、第一番のお客というような形で、見る、見ながら描けるじゃないですか、で、音楽だって聞きながらあるいは演奏し終わってすぐに確認、録音したものを確認してっていうことを繰り返せる、映画だってそうだと。でも、ダンサーってそれが難しい。あるいは、じゃあビデオをすごく活用して、ビデオでいつも確認しないと踊れないとか、あんまりないですよね。そういうこと言う人って。ってことは、どういう意識で見えない自分、あるいは作品が見えないという、ある意味大問題だと思うんですけど、に立ち向かうというか、自分でどういう風にこう腑に落ちる部分を探してるんだろうと思う。室伏さんどうなんですか?
室伏 そうなんだけど、〔…〕逆に聞きたいよ、それはいびつですよ。
大谷 そこは先ほど言われた恥ずかしさという部分に結構ほんとは直結するはずだと思うんですよ。要するに自律できないっていうのはありますよね。音楽は書いた譜面が作品だって平気で言えるわけですよ。鳴ってもいない、鳴らしてもいないものを。そのぐらいなんていうか恥ずかしさがない。
室伏 恥ずかしさっていう風に言っちゃったんだけど、それはあれでしょ? アイデンティファイされちゃうっていう〔…〕室伏鴻は室伏鴻、私は私、っていうもので成立しちゃうものに対する〔…〕実際そうなんであって、それはもう潔く危機を晒し出していくしかないわけ。それを〔…〕ダンスに見せるとか舞踏に見せるあるいはパフォーマンスに見せるってことで引きずっていくっていう力も必要だし、〔…〕難しいと思いますよ。ますます、若い時はこれでいい、これでOKだった、流れもあるじゃないですか、その時間の、最初はノイズを〔…〕自分なりに手ごたえがあるんだけど、今は音楽〔…〕ですけど、〔…〕ノイズを使うってことだけではない、のじゃないのかなあっていう
木村 ノイズも一つの音っていうか音楽みたいにね、限定されてく要素に過ぎないかもしれない。
室伏 一方でその、〔…〕旋律的なものをもってくると非常に情景が成立しやすいですよね。そういう意味では塞がれてるわけ。だから今日は大変ありがたかったですよ。大谷さんが入って下さって。
木村 その塞がるって話で言うと室伏さんいつも何かこうパートナーというかね、今日の白いマスクにした布とか、この床も今日のパートナーかもしれないけど、常にそういうなんかプロップっていうのかね、道具をね、用意して、そこからはじめていく、続けていくっていうのかな。なんかやっぱり自分というものを完結したものとして捉えるんじゃなくて、何かと組み合わせて初めて、これから始められるという、いつもそういう状態を作っているような気がする。そこがやっぱりいいという気がするんだけどね。
室伏 安上がりなんですけどね、大掛かりな仕掛けはあんまりやらないという〔…〕今回の仕掛けも〔…〕できるだけシンプルで、手間のかからないもので済ましとこうという、布一枚ですよね、今日なんか。〔…〕物とからむと面白いし、やってみたら? っていう人もいたし、やればそっちの方がおもしろくなるっていうのも分かるんですけどね。だけど、〔…〕少なくとも音楽くらいは〔…〕ここにもってきて流した途端に、あこれは問題だ、となった。〔…〕響きの〔…〕
大谷 明日はなにか物を使ってみますか?
室伏 使ってもいいですよ。
木村 明日は絶対今日と違うんですよね?
大谷 だいぶこのあたりがあの、明日のパートナーとしてはずいぶん変わりそうなことになってる。何かしら新しい〔…〕がいると。
木村 音っていうのが、今日もそういう話が出ましたけど、
大谷 そう言われるとまた色々。
木村 声とかね。室伏さんの声って、言葉を発する声もそうだけど、「ぐわーっ」っていう声とか、やっぱりすごくユニークですよね。声を徹底するのも面白いかなあと思いつつ。
ベクトルズ:2007-2011年に活動していた佐々木敦、大谷能生、木村覚による批評ユニットのこと
〔中略〕:会話のなかで文字起こししなかった箇所
〔…〕:聞き取りが難しかった箇所
(文責:BONUS、文字起こし協力:三宅香菜子)